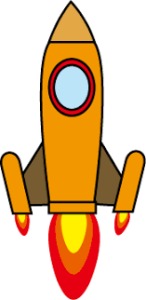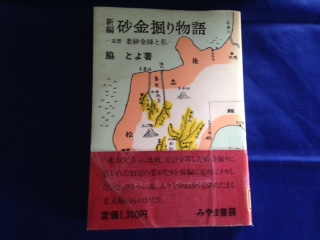この「コラム2018」は、かつて『ブログ:という名のコラム』で公開していたコラムを、今回の会員システムへの変更を機に、「コラム2018」として整理/編集したものです。従って、掲載している内容は以前公開していた内容と殆ど変わっていません。 今から5年ほど前に書いていたコラムでも、今なお通用する記事が多いことに改めて驚かされています。 それは世の中の進歩が遅いのか、いつまで経っても同じことが繰り返されるのか、はたまた私の感じたことが本質を突いているのか、定かではございませんが・・。 < 目 次 構 成 > 1.響く言葉、通り過ぎる・・ (2018.12.30) 2.やおよろずの神々 (2018.12.22) 3. 北海道の日照問題 (2018.12.14) 4.平成天皇と国民 (2018.12.01) 5.相撲というスポーツ2 (2018.11.26) 6.エルニーニョ現象の余波 (2018.11.18) 7.限界集落 (2018.11.12) 8.移民問題 (2018.10.31) 9.鶴来たりなば (2018.10.18) 10.コープさっぽろのアクション (2018.10.11) 11.自然災害との共生 (2018.10.04) 12.相撲というスポーツ (2018.09.28) 13.冬に向けて準備開始! (2018.09.25) 14.北海道のコンビニ (2018.09.18) 15.地震と停電その2 (2018.09.11) 16.地震と停電その1 (2018.09.08) 17.北海道と台風 (2018.08.25) 18.北海道の鮨 (2018.08.22) 19.北海道の二学期 (2018.08.20) 20.終戦記念日又は敗戦記念日 (2018.08.16) 21.お盆という行事 (2018.08.13) 22.オシドリ夫婦 (2018.08.08) 23.北海道移住考 (2018.08.02) 24. お中元 (2018.07.25) 25.土用の丑の日 (2018.07.20) 26.大きなシジミ貝made in TAIKI (2018.07.18) 27.集中豪雨と祇園祭 (2018.07.13) 28. 日出づる国の”御旗” (2018.07.09) 29.宇宙ロケット”MOMO” (2018.07.02) 30.水だこ占いとマーケティング (2018.06.30) 31.気温差18度の移動 (2018.06.27) 32.北海道と夏至 (2018.06.22) 33.昨日のコロンビア戦 (2018.06.20) 34.大阪震度6弱の地震 (2018.06.18) 35.大山鳴動して、鼠・・ (2018.06.15) 36.W杯に期待してよいのか・・ (2018.06.13) 37.氷雨降る、道東南十勝 (2018.06.12) 38.初夏に啼鳥を聴く (2018.06.10) 39.北海道と梅雨 (2018.06.08) 40.北海道十勝のばん馬 (2018.06.06) 41.公務員は誰のために・・。 (2018.06.03) 42.高齢者の運転免許 (2018.05.30) 43.スポーツマンの品格 (2018.05.28) 44.幸福駅跡に神社を・・。 (2018.05.26) 45.日大アメフト問題 (2018.05.23) 46.北海道の鹿、エゾシカ (2018.05.21) 47.W杯日本代表選出 (2018.05.18) 48.脇とよさんの、『砂金掘り物語』 (2018.05.16) 49.行者ニンニク (2018.05.14) 50.十勝にも本格的な春が来たか・・。 (2018.05.12) 51.丹頂鶴のダンス (2018.05.04) |
TV番組を見ていても、目の前に居る人と会話をしていても、街を歩いている時も心に響いてくる言葉と、右から入って左に抜けて単に通過する言葉とがある。
今月のTV放送のニュースを見ていても、それを強く感じることがあった。
一つは平成天皇の85回目の誕生日の談話であった。
平成天皇は、多分これが天皇として最後の国民との談話に成るかもしれない、という思いもあった様で、これまでよりも一言一言の言葉に感情が宿っていたような印象を受けた。
今年全国で起こった自然災害について、被災した国民に対する思いやりの気持ちがTV画面を通じても、しっかりと感じることが出来た。平成天皇の国民に対する想いが、強く感じられたのだ。
更には、自らが撰び相手もそれを受け入れてくれた、人生のパートナーへの感謝の気持ちも強く感じられた。そのくだりは何だか皇后美智子様に対するラブレターの様に、私には感じられた。
あの談話を眼にした皇后は、平成天皇のその気持ちをしっかりと受けとめたのだろうなと、私は想像した。そしてこの人を人生のパートナーに選んでよかったと、心の底からそう思ったのではないかと・・。
平成天皇は、エリザベス女王からもらったアドバイスを尊重し「常に国民と共にいて、国民と共に歩む」といった心情を失うことなくずっと生きてこられたのだと、私は想う。
そしてそれを実践するのに天皇が撰んだパートナーは、まさにうってつけの相手だったのではないかとお二人の行動を見ていてそう思うし、今回の談話を聞いてまた私はそう感じたのである。
時折目を潤ませ、言葉を震わせながらの談話は私の心の中にすっと、すんなりと入って来た。私の心に響いてきたのである。
平成天皇は真面目で真摯な人柄だと思う。
そしてその故に、多くの国民からも慕われているのだと・・。
それから何日か経って、今年6年目だかを迎えた行政の長のコメントがニュース番組で放映された。早口でしゃべり目線もカメラに向かっていなかった彼の言葉は、軽く右の耳から入ってさっと左の耳から出て行った。心に響かない言葉であった。
数の力を武器にいくつかの法令を熟議をしたとは言えないまま、強行採決を繰り返し実現させた彼は、自分の政治信条に対しては忠実であったかもしれないが、決してそれ以上では無かった。
法律が成立した後、繰り返し彼が言っていた「これからこの法案について国民や議会に丁寧に説明して行き、理解を得るようにしたい」といった言葉は、その場しのぎであって実際には言葉通り実行されたことは殆どなかった。
世の中には、その場しのぎに耳触りの良い言葉を発し、当面の課題をやり過ごせれば「あとは野となれ、山となれ」という人種が少なからずいる。
通常の人間関係や企業・組織においてそう云った人種は、信を失い相手にされなくなりその人の言動に耳を貸すこともなくなる。
しかし不思議な事に、政治家の世界ではそういった人種は相変わらず市民権を得て、ぬくぬくと生存を許されている。そしてだんだん面の皮は厚く成り恥を忘れる。厚顔無恥である。
そういう人種の言葉は軽く、心に響かない。
心に響き記憶に残る言葉を発し、共感を以って受け入れられる人物への評価は、歴史の風雪にも耐えられるのではないかと私は想っている。
それに引き換え、心にも響かず記憶に残らないその場しのぎの人物への評価は、歴史の評価に耐えることは出来ないであろうと思う。きっと彼の存在は遠からず忘れ去られるであろうと思う。記録は残したとしても、である。
そのような事を感じた今月の、対照的な二人の談話であった。
もうすぐクリスマスが始まり、そしてやがてお正月がやって来る。
日本人の殆どはキリスト教徒でもないのにクリスマスを祝い、神道の熱心な信者というわけでも無いのに、初詣でを行い氏神や産土(うぶすな)神に祈り、お正月を祝い楽しむ。
子供の頃や青年期の頃はこのことを矛盾と感じながらも、それぞれの行事に参加し、それなりに享受してきたものである。
それから年を重ね還暦を通過し、日本人の宗教観なるものがうっすらと判り、鎌倉時代の武将を通じて神社や仏閣との関わり、更には神事・祭事といったコトについて調べ理解するように成ってから、なんとなく矛盾を感じなくなって来ている。
キリスト教徒や、イスラム教徒・ユダヤ教徒といった一神教の信者達は、自らがあがめる神というのはただ一つの神様としている。という事は同時に他の神様や宗教は邪神となり、彼らの中の積極的な信徒は他の神様や宗教、ひいてはその信徒たちを積極的に排除・排斥しようとする。
イスラム過激派やキリスト教徒の過激派、ユダヤ教徒の過激派といった種類の集団が誕生する宗教的な意味での背景は、こういった事に起因している。
それが過激な宗教指導者や民族主義者、更にはそれを利用して自らの権力の行使に使おうとする政治家が現れた時に、十字軍のイスラム教徒攻撃や異なる宗教への魔女狩り、ヒトラーのユダヤ人排斥、ISによるテロ行為の正当化、更には明治維新の廃仏毀釈や国家神道の唱導、といった様な事に成る。
しかしながら、それら宗教指導者の純粋すぎる衝動による行動や、政治的指導者の国家・国民の統制欲は、長続きする事もなくせいぜい数十年で破綻し、消滅する。
純粋すぎる宗教的行為は、その純粋さのゆえに排他的であり唯我独尊であるために、息苦しいし、現実世界の持っている多様性や複雑さに適応できないからである。
古代や中世のようなオールキリスト教徒対オールイスラム教徒、といった単純な構図の時代においてすら、この異教徒間の戦いは長続きしなかった。
現代の様に人も物も・情報も瞬時に世界と結びつき、同時進行的に地球規模で物事が共有化され、影響し合う社会では長続きしないであろうし、受け入れられなく成ってきている。
今日の人類の到達点においては、多様性や複雑さ、異なる価値観や美意識、多民族との併存・共存といった事を前提にしないと、多くの市民や国民更には世界の人々に支持されることもなく、共感も得られなくなっている。
さてそんな中での日本人の宗教的行事に対する行動である。
私は一言でいえば「やおよろずの神々」の存在を受け入れ、八百万の神々の存在を至るところで、いかなるタイミングにおいても受容する、日本人の宗教観や価値観といったモノが現代社会にとっては有効ではないか、と感じている。
この多様で異なる価値観や美意識が瞬時に、同時進行的に飛び交う社会において、日本人の持つ多神を認め受け入れるという、「やおよろずの神々」的価値観は実に有効で受容可能なモノであると、私は思う。
日本人にとっては、クリスマスも初詣もお祭りもお盆(精霊祭)も何んでもありなのである。その時々場面々々に応じて信仰の対象=神様・仏様が変更し、移り替わって行く。
そういった多様性を認める宗教観や生活感が、これからの地球市民にとって、共通の価値観として認められ、大切にされるのではないかと、そう思っている。
自らのご先祖様はもちろんの事、竈の中にもトイレにも神様がいて、奇岩や景勝の中にも神様を見出し、お天道様をも尊敬し崇拝する。それぞれの場所それぞれの対象に価値を見つけ、崇(あが)め奉(たてまつ)る。
こういった日本人的な価値観や宗教観を私は受容し尊重する。
という事で、私は今年もクリスマスにはケーキを買って食べ、お正月には初詣をすることに成るのである。
北海道の面積が、九州の二倍近くあることは以前にも触れてきたが、言うまでもなく北海道の面積は広い。そしてそのために北海道の気象環境もいくつかに区分しなければ、理解する事はできないであろう。
これもまた以前触れていると思うが、日高山脈によって北海道は東部と西部とに大きく区分される。すなわち日本海側と太平洋側とに、である。
この関係は東北地方が奥羽山脈によって区分されるのと同じである。
東側は比較的に晴天が続くのに対して、西側は曇天が多くロシアあたりから廻って来る寒気団の影響を一番受けるのだ。北風である。
従って、道央や道南と云われる札幌や小樽、函館といった北海道では大都市に当たる地域はおおむね西側に立地していることから、寒気団の影響を受け易くなっている。
それに対して私が住んでる十勝は日高山脈の東側に在ることから、冬ではあっても晴天の日が多く続く。
11月中旬から4月下旬ぐらいまで続く北海道の冬であるが、おおむね西側の地域では7・80%は曇天が続き、週に何回となく雪にも見舞われる。
一方日高山脈の東側では7・80%は晴天に見舞われるのである。その内まともな雪が降るのは月に4・5回あるかどうかだと思う。
従って、札幌あたりの気象情報を全国放送で公表していても、その情報が道東地方に当てはまることは、ほとんどない。
本州在住の友人たちがたまにくれるTelで心配されることがあるが、この関係をご存じないから勘違いされることが多い。
私は3日程前に「大人の休日クラブパス」というJR東日本とJR北海道が、年に数回企画する5日間の電車乗り放題の切符を購入して、関東から新潟経由で帰って来たのであるが、函館や長万部・苫小牧といった場所を経由して札幌に寄ってから、十勝帯広に帰って来た。
その際に痛感したのは今回のテーマでもある「日照問題」であった。函館から札幌そして日高山脈の山頂に近いトマム辺りまでは、将に曇天が続き雪がちらついていた。
そして十勝帯広辺りでは小雪がちらつく程度であったが、南十勝の大樹町に着いた翌日からは今日も含めて、連日晴天が続いている。
気象情報によると札幌や函館・苫小牧といったエリアはここしばらく雪が降ったりやんだりの日々が続く、という事であった。
私は道南や道央と云われるエリアで3日ほど過ごしたのであったが、その間気持ちもどんよりしていたことを思い出す。
その間中思ったのは、半年もこんな天候が続いたら気鬱に成ってしまうかもしれない、という懸念であった。
あと数十年後に自力で車が運転できないように成ったら、現在の自然環境豊かな田舎暮しが続けられないのでは、とひそかに想っている。
私はその頃には都市交通のインフラがある程度整っている街への、移動を検討しているのだが、その際この日照問題が大きな選択基準に成ってくるかもしれない、と思っている。
半年間曇天の続く生活が私に耐えられるかどうか、それが問題なのである。
来年に迫った平成天皇の退位と新天皇の即位に伴い行われる儀式についての話題が、昨今注目を集めている。
きっかけは次の実質的な皇太子に就任する、秋篠宮親王の53歳の誕生日に寄せた談話である。話題のテーマは天皇の交代時に行われる「大嘗(だいじょう)祭」という、皇室にとって重要な儀式に関してである。
秋篠宮親王の主張は、現行の憲法に則り「大嘗祭」は天皇家の私的な宗教行事であるから、国家予算という公費を使わないで、皇室の私的な費用としてその出どころも皇室の年間予算なりから賄うべきだ、といった主張のようだ。
私の推測ではこの考えは秋篠宮親王個人の意見であるというより、平成天皇一家の総意なのではないかと、そんな風に感じている。
日頃の天皇一家の言動や行動を見ていると、私はそんな風に感じるのである。
平成天皇は、人生のパートナーである皇后を撰ぶ時から従来の慣習や慣行に拘わらず、自分の考えや意思をしっかり持ち、その信念や考えを心中に据えて行動し、それを敷衍(ふえん)しているように思える。
独りの人間として、自己形成がしっかり確立されているように思われる。
その平成天皇の価値観の根っこには、戦後の民主主義国家体制における天皇の役割や機能についての、自分なりの明確な考えがある様に思われる。
以前見たTV番組のことを思い出す。
終戦から間もない平成天皇が皇太子の時、英国のエリザベス女王を訪れ、女王に民主主義社会における王室(皇室)の在るべき姿を問うていた、といった内容のものであった。
当時の皇太子は戦後の新憲法の下での、「皇室の在り方について」や「あるべき姿について」真剣に考え、模索していたのではないかと思われる。
その問題意識が強くあったから、エリザベス女王を尋ねたのではなかったかと思う。
そしてその機会に、当時の皇太子は女王から的確なアドバイスをいただいたのであろう。
そのエリザベス女王のアドバイスを自問し熟考した結果、そのアドバイスが適切であると考え、それ以来ご自分の行動様式の根っこに据えたのではないか、と思われる。
その根っこに据えた価値観を大事にして、現在の人生のパートナーを撰び、皇太子時代を過ごし、平成天皇に成ってからも尚ご自分の行動規範として尊重し、実行し確立し続けて来たように思える。
国民が主役の国家イベントに積極的に参加し、第二次大戦で犠牲に成った人々の鎮魂に訪れ敬い・哀悼の想いを伝え続けている。
大きな地震や災害があれば率先して見舞いに行き、温かい言葉を被災者に投げかけ励まし続けている。先日も北海道の震災被災地を訪れている。
80代半ばにしてもなおご夫婦で実直に・勤勉に実行し続けている。
そしてその行為に多くの被災地の人々は癒しを感じ、勇気をもらっているようだ。
当時の皇太子がエリザベス女王から頂いたアドバイスは
「常に国民と共に生きる」といった内容だったと記憶している。
17世紀から民主主義国家と共存してきたイギリス王室の教訓である。
平成天皇及び皇室のメンバーの行動基準の根っこには、こういった考え方がある様に私には思える。昨今の秋篠宮親王のご発言はそう言った価値観に根ざしているのではないかと、私は推測している。
「常に国民と共に生きる皇室」という事は、常に国民の目線で、国民の立場に立って考えて行動する、という事だと思う。
その皇室の価値観が今回の「大嘗祭」という儀式に際して、宮内庁という行政庁の官僚の前例主義や、慣習・慣行の過度な尊重とは相いれなく成っているのであろう。
そしてまた、がちがちな保守である現在の政権とも、相いれないのではないかと思う。
なぜならばその行動基準は「常に国民と共に生きる」皇室であることを標榜しているからであろう。
旧弊の踏襲や前例の継承に重きを置いている行政官僚と、その存在を自分たちの政権のイデオロギーに使いたがる保守勢力との乖離(かいり)が、昨今の政権主催の行事と皇室との間の齟齬や距離感を生んでいるように、私には思える。
先月行われた明治維新150周年の行事に、皇室からの参加が無かったのもこの乖離の現れではなかったかと、私は想っている。
この政府主催の記念行事は、長州藩の出身であることを強く意識している現総理大臣がリードし、保守派の明治政府にノスタルジーを感じる人々が参加したが、多くの国民の共感を得ることの無かった、盛り上がりの欠いた寂しいイベントであった。
昨日本年最後の大相撲、九州場所が終了した。
結果はご存知な通り貴景勝という、縦・横・高さがほぼ同じに見える立方体の若武者が優勝した。ゴムマリの様によく跳ね動く力士で、あの立方体でブチカマシをすると相手はたいてい腰が砕けてしまうようだから、相当の破壊力があるのだと思われる。
かつて小錦という力士が居て、大関迄上り詰め強烈な突き技である「プッシュ」で相手を土俵外に跳ね飛ばしたものである。その小錦が何となく重なる力士である。
その彼は勝敗の結果をあまり顔に出さないタイプで、横綱の鶴竜あたりと同じタイプなのかもしれない。
22歳という若さで13-2という成績は立派だったと思う。父親の薫陶を受けて相撲道を迷わず目指してきたという。
その彼にとって今場所は、格別の想いがあったのだと思う。
師匠の貴乃花の迷走により貴乃花部屋が解散し、師と仰ぐ師匠自身も引退という結果に成っていたからである。
その貴乃花部屋に在って、22歳の若さで小結として所属部屋力士の先頭を走って来たのである。心に期するものが在ったのではないかと想う。
その想いが強かったが故に、勝敗に一喜一憂せず今場所は闘い続けて来たのではなかったか、などと想って童顔のポーカーフェイスの心中を察した。
苦労は若いうちにした方がその人間を大きく成長させることに繋がるのではないかと、私は常々想っているが、彼の歩む道も平坦ではないだろう。
あの立方体の身体から繰り出すブチカマシやツッパリ、押し相撲がどこまで、そしていつまで通用するか判らないが、これからも注視していきたい力士の一人ではある。
ひとまずは優勝おめでとう!
今日我が家では半年間お世話に成った、ビニールハウスのビニールを外した。GWの終わり頃にご近所のお力を借り設置したビニールハウスであるが、半年たったこの時期に外すことに成ったのである。
例年であれば11月の初め頃に行う行事であるが、今年は暖冬のために二週間ほど遅れている。全国の天気予報でも時折北海道の暖冬については報じられることがあるから、ご存知の方もおられるだろう。
そしてその暖冬の原因は表題の「エルニーニョ現象の余波」という事らしい。
赤道近辺の南米が今年は暖かい事で、日本の偏西風の流れる位置が平年よりだいぶ押し上げられている、という。
偏西風という名のジェット気流が平年だともっと本州の半ばまで下っているのが、今年はエルニーニョ由来の暖冬により北東北の上部あたりを流れるのだという。
その偏西風にブロックされて北極圏由来の寒気団がなかなか南下しないという事らしい。
という事で、今年は例年より寒気の到来が遅れているというわけだ。
我々の様に関東の南部エリアから北海道に移住してきた人間にとって、この暖冬はありがたいものである。ビニールハウスで造る手作り野菜の恩恵にあずかっている身としては、秋野菜を二週間ほど長く味わえることにもなる。
また、灯油の高騰という現実に直面している身であれば寒波の到来が遅くなることは、家計を助ける事にもつながる。
その寒気も今週辺りからいよいよこの南十勝にも到来して来る、との予報である。
先週あたりから最低気温が氷点下を行ったり来たりし始めている。そんなこともあって今シーズン初めて床暖房を使い始めた。
我が家の暖房はこの床暖と、ペレットストーブとによって賄われている。ペレットの方はひと月ほど前から、朝夕の寒さが感じられる頃から使い始めた。
両者の違いは何かというと、限定的な空間を温めるためのペレットと家全体を温める床暖房との違いにある。
従ってこれから本格的な冬が到来し、家全体がマイナス二桁台の外気にさらされる季節には家全体を温める、床暖房の存在が不可欠となる。
本州の温暖なエリアに生活している人は夏場に経験していると思うのだが、外気が30度を日常的に超える時節は一日中冷房を効かせ、家全体をずっと適温に冷やしておけば余分なエネルギーを使わずに済むという事があると思うが、それと同じである。
寒冷地に在っては、床暖で家全体をある程度暖め続ければ外出から帰って来た時に家全体を温めるための、余分なエネルギーを使わなくて済むことに成るのだ。
一旦冷え切ってしまった家全体をある程度まで上げるためには、その都度相当なエネルギーの消費が必要になるからである。
従って、寒冷地で冬を過ごそうと考えている向きには、ペレットストーブと共に床暖房は生活インフラとして不可欠な存在であることを知っておくとよいかもしれない。
もちろん、ペレットストーブよりは薪を使った暖炉の方が、数倍愉しいのであるが現時点では我が家ではペレットストーブで生活している。
10数年前にこちらへの移住を考えた始めた時に、薪ストーブを使った宿に数日お世話に成ったことがある。その時の体験から言えばペレットストーブよりも薪ストーブは数倍愉しい。
特に男たちにとっては薪ストーブの暖かな炎を見ていると飽きることがない。
いつの日か薪ストーブの暖炉を導入したいと思いながら、これからの本格的な冬の到来に備え始めている今日この頃である。
薪ストーブ ペレットストーブ
先週は5日間ほど新潟県に、次作のための取材に行ってきました。
今週中に公開予定の『安田義定父子と、甲斐之國・越後之國』の情報収集のためです。
晩秋の新潟への取材旅行、と言っても鎌倉時代の安田義資公の痕跡や足跡を求める旅なので、平安時代や鎌倉時代に國府・國衙の在った上越地域に限られています。
新潟市や長岡市の在る中越や村上市などの下越は今回は立ち寄りませんでした。
この物語のために新潟を訪れるのは今回で3回目で、これまでの調査や取材では行き切れなかった場所や人物に逢ってきました。
対象はいつものように「八幡神社」「金山神社」「駒形神社」「国分寺跡」といった神社仏閣と図書館が中心で、郷土史研究家にもお逢いし情報交換をしてきました。
更に「祭り」や「神事」「行事」につながる情報収集も欠かせません。
上越では「祇園祭」と「舞楽=神楽」とに大きな特徴があることが判り、それなりに調べたり取材することが出来ました。
今回の上越探訪で痛感したのは、山間いの村々での人口減少と住民の高齢化の進展です。
若い人達の都市部への人口流失は、働き場所の確保と現代風の生活様式の享受のためには防ぎようのない流れなので、このトレンドを防止することは出来ないだろうと思っています。
翻って私自身、故郷を顧みることなく大学を卒業後は、都市部を中心に転々として来たことから、他人に対してどうこう言うつもりもありません。
しかしながら若者の流失や地域住民の高齢化という事が主たる原因となって、かつて村々やそれぞれの地域で、数百年は続いて来たであろうお祭りや神事が、担い手不足や担い手の不在・消滅という形で、失われていくことや途絶えて行っている現実は、とても残念な事だと思っています。
山間いの村々や、中心市街地から遠ざかるエリアに成れば成るほど廃屋が目立ち、目にする人々は老人や高齢者が中心に成って行きます。
それらの地域では、かつて賑やかに行われた祭りや神事も行われなく成っていたり、神社そのものの荒廃が目立つように成っています。
そういった現実を眼にし、耳にするたびに残念な気持ちでいっぱいに成ります。
そして限界集落という最近よく聞くこの言葉が頭をよぎり、このまま行ったら各地で何百年もの間守られ伝承して来た神社やお寺、そしてそれに関連する祭りや神事・行事といったコトは、これから先いったいどう成ってしまうのだろうと、想わざるを得ません。
私は今、安田義定という八百年前の平安末期の武将の痕跡や足跡を探したり尋ねたりしていますが、私とは違った関心領域をお持ちの方や、違った立ち位置の方がたくさん現れて、遠からず忘れ去られてしまうかもしれない、神社や仏閣に足を運んでいただいて、何らかの形でその神社仏閣の神事・行事の存在意義や、歴史的な価値などを記録したり、掘り起こしたりして欲しいものだと、願って止みません。
いつか担い手が消滅しても、記録が残っていれば振り返る事や思い起こすことが出来るであろうと思われるからです。
かつて行われていて、今では途絶えてしまった祇園祭の山や鉾について、丁寧に探し当て掘り起こし、記録した若原史明氏が『祇園會山鉾大鑑』を取りまとめ、後世に残して来たようにです。
そういう意味では、私は各地にいらっしゃる郷土史研究家の方々の働きに、大いに期待を寄せています。
そして私自身は、安田義定という忘れ去られた平安末期から鎌倉初期の武将にこだわり続けることで、彼につながる埋もれた神社や仏閣、更には神事や祭りを調べ掘り起こし続けて行き「歴史検証物語」という形で記録し残して行きたいと思っています。
そのような事を痛感した、五日間ほどの晩秋の上越地方の旅でした。
昨今アメリカ大陸では、USA移住を目指している移民希望の中南米人の行進(キャラバン)が話題に成っているようだ。移民の国アメリカでこれ以上スペイン語を話す移民を受け入れないと、声高に叫んでいる花札大統領の、来週に迫った中間選挙対策との衝突が今、世界の耳目を集めているのだ。
またヨーロッパでも、この2年間の間に100万人ほどの移民を受け入れて来たメルケル首相の政治的な基盤が、今月行われた二つの州議会選挙で揺らいできている。その最大の争点はどうやら移民問題であるようだ。因みにメルケル政権は今年で13年目だという。
そして我が日本である。先日始まったばかりの今国会においても、外国人労働者の積極的な受け入れ政策を推進する法律が、主要議題に成るようである。これもまた一種の移民政策であろう。
翻って我が国の歴史を紐解けば、古代までの日本は移民大国で、その移民達によって国家の骨格が形成されて来たといっても過言ではない。
『日本書紀』や『續日本記』などを読んでいると、実に多くの渡来人がやって来て、日本に定着してきたかが詳細に書かれている。
私がこの夏に書き上げた京都の祇園神社にしても然りである。蘇民将来という渡来人がかの神社の祭神である事は広く知られている通りである。
また、宮崎の高千穂辺りの「高天原」に定着したとされる、天皇家の祖先もまたアジア大陸から遅れてやって来た渡来人であるようだ。
更にその後の「継体天皇」という、名前からして当時の王統を別系統の人間が継承してきた事を現わしている天皇は、福井県敦賀の気比辺りの豪族出身で、それより更に遅れてやって来た大陸の渡来人だという。
してみると日本という国家もまた、実に多くの大陸からの渡来人や移民によって、形造られて来たかが判るのである。もちろんそれらが活発に行われていたのは今から1,200年以上前の事ではあるのだが・・。
ドイツのように人口の1%以上に及ぶ移民をわずか2年間の間に受け入れたという、急激な移民政策が少なからぬ摩擦を引き起こす事は仕方ないとは思うが、だからと言って外国人の流入をいつまでも拒み続けることが出来ないのも、現実であろう。
グローバル化が進む現代世界の現実と、少子化社会の進展、更には日本の歴史を鑑みれば移民受け入れは無理からぬ事であろうと、思わらざるを得ないであろう。
TVのニュース番組などを観ながら、酒を飲みつつそのような事を思ってしまう私なのである。
冬遠からじ・・。
我が道東南十勝大樹町にも、丹頂鶴の姿が目立つように成って来た。
30羽前後は来ているようだ。少なくとも私が確認した数はそんなものだ。
早朝、丹頂鶴は編隊をなして7・8羽「クック~ッ、クック~ッ」と、しり上がりの高い声を上げながら中空を飛んでやって来る。
朝食を食べに群れを成して、刈り入れの終わったデントコーン(トウモロコシ)や牧草地に向かうようだ。
刈り入れの終わったそれらの畑地には、大きなトラクターが収穫時に取りこぼしたトウモロコシを初めとした穀物の実が、そこここに散らばっているらしいのだ。
例年10月の中旬頃に成ると丹頂鶴を初め白鳥なども、シベリア辺りから越冬のためにって来るのである。
そのうち丹頂鶴は大樹町の湖沼などを中心に春先まで定住する事が多いが、白鳥などはここから更に南下して行き、道南辺りまで行ってから津軽海峡を渡り、本州まで行って冬を越すように成るようだ。
道南渡島でも津軽半島や下北半島に最も物理的に近い「知内町」や「函館」辺りから本州に渡ることが多いようである。
大樹の市街地に買い物などの行き帰りに丹頂鶴のグループを見かけることが多くなると、私達はそろそろ本格的な冬がやって来ることを、意識しだすのである。
移住以来の10年近くの経験で学んだことである。
今朝は家人がこのシーズン初めての床暖房を入れた。最低気温が一桁台の前半に成ってきたことにも依る。
昨今の灯油高騰を気にしながら、我が家では冬の到来を実感しているのである。
北海道の生協であるコープさっぽろが、今回のブラックアウトに対する損害賠償を北海道電力に請求することを検討していると、新聞報道にあった。
その報道では、今回のブラックアウトの直接的なきっかけは、震度7の地震であったとしても、ブラックアウトそのものに関しては、北海道電力という一法人の企業責任による人災である、という問題意識があるようである。
具体的には、苫東厚真火力発電所に対する一極集中を是正しなかったことや、広大なエリア北海道の電力システムを道央に集中させてしまっている点、更には自然再生エネルギーの購入を抑制している点等を、問題視しているようだ。コープさっぽろのそれらの問題意識は先月私自身が指摘してきたことと重なる点が多いので、ほとんど同感である。
北海道電力は一民間企業ではあるが、北海道において現時点では独占企業であり、全道民の生活に必要不可欠な電気を発電し・送電し・供給している電気事業の一気通貫法人である。従ってその法人としての企業活動は「ガス」「水道」等と同様に、北海道民の生活インフラそのものと言ってよいものである。
であるが故にその経営の社会的影響力は非常に高く、社会性の高いものであり、同時に事業者としての社会的責任は常に重い。
今回のブラックアウトを引き起こしたことに対して、北電の経営者が経営責任を問われなければならないのは、その法人としての性格・影響力からいって、当然と言えば当然のことなのである。
今回のコープさっぽろのアクションは、北電のこれまでの電力事業における企業行動が適切であったかどうかが、法廷の場で広く問われ、議論・争われることに成るであろう。
そういう意味では、北電の稚拙な危機管理能力によってブラックアウトを経験した我々道民の想いを代弁してもらえていると、私は想っている。
と、ここまで書いたところで、今度はそのコープさっぽろの「損害賠償請求」の話がどうやら、立ち消えに成りそうである、との報道があった。
その理由は、組合員からの反応やSNSなどで、今回の生協の動きに対してネガティブな意見や、慎重な対応を求める声が少なからず出ているから、だという。
残念な事である。
生協の組合員にもいろんな立場の人はいるだろうし、いろんな考えの人はいるだろう、更には北電と利害関係を持っている人だって、少なからず居るに違いない。
私が残念に思っているのは、生協の腰が据わっていないことに対してである。
今回のブラックアウトに関しては、北電の電気事業者としての経営責任が問われることは、避けて通れない問題であろう。
北電に損害賠償を求めるのは、損害金の補償といった点もあるかもしれないが、それ以上に北電の電気事業者としての適性や経営能力の瑕疵についてを、法廷で問い・明らかにすることでもあるだろう。
そのような社会的な意義があるからこそ、生協も今回の損害賠償請求を行おうとしたのではなかったのか?
そういえば連合という労働組合の連合体は、傘下に原発や電力事業法人の労働組合員がいるから原発廃止についての明確なメッセージを出せないでいるようだ。それと同じような構図が生協の中でもあったのだろうか?
もしそうであったとしたらとても残念である。
北海道の地域に根差した、道民の生活に密着した生協という立場をとり続けるのであれば、多少の雑音が入ったとしても、当初の問題意識を大切にしてもらいたいものである。
それかこの程度の横やりが入ることを事前に想定して、賠償責任を問うかどうかを内部協議で熟議してもらいたいものである。
因みに生協は「コープ電力」という事業も手掛けているようであるが、それも売電による収益向上といった点に事業の目的があるのか、北電の独占的な電気事業への別の選択肢を道民に提供しようとしているのか、そういった点についても内部で熟議してもらいたいものである。
今回のブラックアウトを経験して、北海道のコンビニ「セイコーマート」の災害への事前準備や、ブラックアウト時の対応に感心したものであるが(*)、「コープさっぽろ」の対応はまだまだ腰が据わってない印象を受ける。
生協は「セイコーマート」から、もう少し学んだほうがよいのかもしれない。いろんなことについて、である。
*ご興味のある方は「09/18:北海道のコンビニ」をご参照ください。
颱風が毎週のようにやって来る。
先週は24号で、ちょうど十勝から関東に仕事で向かう日程に重なった。午後一の飛行機は颱風の影響がまだなく、直前まで気をもんでいたがスケジュール通りに飛んで、無事に羽田に到着することが出来た。
その夜の飛行機はさすがに運休したようで、息子の家で聞いた颱風の強い風は大きな音をたてながら明け方近くまで、唸り声をあげていた。
翌朝からは颱風一過の晴天で、一件落着かと思ったらこの週末には、次の颱風25号がやって来るという。
実は今から1か月ほど前の台風21号の時に私は次の物語の題材を求めて、越後新潟に行っていた。四国→関西→北陸→日本海というコースを通り、関空が大きなトラブルを起こしたあの颱風の時の事である。
新潟の上越地方を中心に4泊していたのだが、その際に21号が輪島辺りから佐渡島に抜けた様である。
そのルートは当然上越を通過したのであった。
颱風が接近した時刻私は市立図書館に籠って、ひたすら資料を読み漁り、コピーを続けていた。
そして台風が通過した次の日の未明には、家のある北海道が大地震に見舞われれた。
といっても我が家のある南十勝は、震源地からは150kmほどは離れていることから、震度4で済んだようだ。
従って、地震の影響は殆ど無かった。影響があったのは停電の方である。電気が通じる迄2日ほどかかった。
今回の24号の影響が、遠州のかつての安田義定公の領国である遠江之國辺りでは、今でもまだ続いてるらしい。4日以上停電が続いてるとの事だ。送電網が被害を受けたのだろう・・。
私はたった2日間の体験であったが、停電による日常生活の不自由さというか不便さは身に染みている。
先ずは遠州の方々に、お見舞い申し上げる。その不自由な生活に対して・・。
森町周辺にはお世話に成っている方々もいるのである。
しかし北海道に居ても遠州に居ても、はたまた沖縄に居ても自然災害の脅威は避けて通れないであろう。
人間の都合に関係なく、自然の営みは続いていくしその影響がもたらすパワーは、人間にとって必ずしも良い影響ばかりではないからだ。
従って、私達人間はその自然災害が起こり得る事を常に考慮して、自分たちの生活のあり方を考え、折り合いをつけていくことを考えて、生きて行くしかないのである。望むと望まないとに拘わらず、である。
7月の集中豪雨やこの夏の度重なる颱風、そして大地震それらに遭遇している人達が直面している事は、明日の自分自身の問題なのかもしれないし、来年自分が遭遇するかもしれない課題、なのかもしれないのである。
颱風や地震による災害の報に接するに当たり、もう一度今の自分が生活している自然環境を、謙虚に見つめなおすことも大事だと思う。
私自身では、この前の地震に伴う停電を通じて、その事を改めて考えてみたのであった。
その上で、日常生活を最低レベルで維持するために必要不可欠な、家庭生活インフラを確保するように、手を打ち始めたところである。
度重なる颱風の上陸を前に、自然災害と共生するために今何をやっておくべきかを、改めて考えてみるのも良いのではないかと、私は想うのである。
つい先日大相撲の秋場所が終わったところである。
今場所は結果的には白鵬の全勝という形で、優勝者が決まったわけだが優勝争いは決して一方的なものでなく、最後まで複数の力士が優勝を争い絡み合った事で、なかなか楽しく見させて貰うことが出来た。
私自身は小学生のころまでは割と相撲が好きで、ラジオやTVを通じて好く観もし、聴いてもいたものだったが、中学生のころから遠ざかることが多くなって行った。サッカーが興味の対象に変わったこともある。
それに所謂伝統的なスポーツに対して、何となく距離感を抱くようになった。
これはまぁ相撲に限らずだが、思えばそれは自我の確立や自己の人格形成確立、といった事にも関係していたようにも思える。
その頃私はそれまで馴染んできた事や、当たり前な事として無条件で受け入れてきた事&価値観に対して、一旦立ち止まって考え、見つめ見直す、といったスタンスを取り始めたのであった。
それはまた既存の価値観や、その時点での支配的な価値観に対し、疑問を呈すという事をも意味していた。その行為は私自身の成長のプロセスには望ましい事だったと、今では振り返ってそう思う。
若いころは体力はもちろん気力も充実していて、新しい事にどんどんチャレンジする事が十分可能だったからである。そのためには既に出来上がった価値観や、確立していたそれまでのノウハウに対して疑問を抱くことが、それらを打ち破るエネルギーの源にも成っていた。
そして何よりもまた、当時の私には時間がたくさん残されていた。
これまで生きてきた時間よりもこれから待っている時間の方が長く、ほとんど永久的に将来が続くのではないかと、錯覚もしていた。
自分の人生が有限であり将来というのは、これまで生きてきた時間程度しか残されていないのではないかと、そんな風に考えるようになったのは40歳を過ぎた頃であった。
それはまた体力や気力の衰えを意識するようになった事とも無縁ではなかった。
それ以上に自分の能力の限界を痛感するようになり、何にでもどんどんチャレンジしてく事に限界を感じたこともまた、無縁ではなかったようである。
何回もチャレンジをして、その都度限界にぶち当り挫折を経験する、といった事を繰り返しながら、ようやく自分という人間の輪郭がぼんやりと見えるようになったのも、やはり40前後ではなかったかと思う。
30代の後半に他人より遅くではあったが、家庭を持ったことも多少は影響をもたらしていたのかもしれない。
さて、そんな私が再び相撲に関心を抱くようになったのはここ6・7年のことである。
八百長相撲がマスコミで取りざたされて、その後東日本大震災があって力士達が被災地を慰問で訪れ、被災者たちを励ます姿を報道などで見聞きするようになった頃からであった。
力士たちの慰問という行為が、被災者たちにとって少なからぬ励ましや癒しに成っていることを目にして、私自身もう一度相撲を見るようになったのである。
4・50年ぶりに改めてみることに成ったそのスポーツは、サッカーなどのスポーツで見慣れた所謂チームプレーとは、趣を異にする全く個人のスポーツであった。
一人の力士が自分独りで、自分のために闘い、時には自分自身と闘っていたのであった。
おしゃれなユニフォームやウエア類&シューズといったものは全く身に着けず、ユニークなヘアスタイルもそこには何も無い。
もちろん胸や肩の周りにはスポンサーのロゴも見当たらない。
まさに裸一貫で、伝統的に定められたちょんまげを 生やし、マワシという名のふんどしをまとっているだけである。
ある種の新鮮さを感じたのである。
それ以来私は大相撲を定期的に見るようになった、と言っても私が見始めるのは17時15分頃からの、中堅以上の上位力士たちの相撲であるのだが・・。
私はこれまで同様チームスポーツの典型であるサッカーを見続けることは止めないしまた、全くの個人スポーツである相撲を見ることも止めないであろう。
両方とも私をワクワクさせてくれるし、十分楽しませてくれるからである。
さて、翻って貴乃花は今、いったい誰と闘っているのであろうか・・。
日本相撲協会という組織か、それとも一部の考え方や価値観を異にする親方や理事達であろうか、はたまたそれとも自分自身であろうか・・。
昨今のマスコミ報道を見たり聞いたりするにつけ、私はそんなことを考えるのである。
昨日から今日にかけては所謂「中秋の名月」という事に成るらしい。
一年で最も美しく月を愛でることが出来るとのことである。
確かに昨晩観た月は美しく時折雲が架かったりしてはいたが、清少納言などによるとその方がかえって美しいという事に成るようで、確かにそのようでもあった。
私の住んでいる大樹町の郊外というか郡部は、山間部ではなく海に近いエリアという事もあって、夜に成るとホントに星がきれいである。もちろん雲が架かってないことが前提であるのだが、周辺に殆ど人家が見当たらないこともあって、夜間は星が沢山かつ大きく見ることが出来る。1㎞四方に2・30軒という過疎だから、星空を遮るものは全く無いのである。
従って昨日も中秋の名月を確認する事は出来たが、雲が架かっていたこともあって、あまり長くは鑑賞する事も無かった。
そしてこの日曜日はまた、秋分の日でもあった。
よく「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるが、この言葉は北海道でも通用する。
しかし北海道の場合は、春分よりも秋分の方がより的確だと感じることが多い。
北海道では「春分の日」前後の3月下旬と言えば、まだまだ春を予感させることは無い。家の周りの根雪は1m以上は積もったままだし、日方(ひかた)と言われる暖かい南風もまだ吹かない。
その辺りは本州(北海道弁では内地)とは少なからぬ開きがある。根雪が解けて日方が吹き始めるのは4月に入ってからであり、本格的な春の到来が感じられるのはGW頃である。内地とは1か月はズレて、遅れて春はやって来るのだ。
ところが秋分の日は違う。
秋の彼岸を境に北海道では最低気温が、ぼちぼち一桁台になり始める。最高気温はまだ20度前後を行ったり来たりしているが、いずれにしても朝夕に寒さを感じ始めるのは確かである。
そういった事があるから秋の彼岸が過ぎると、そろそろ冬に向けた準備を始めるのである。
春から夏にかけてお世話に成ったビニールハウスのビニールを外す日取りも考え始めなければならないし、ペレットストーブの燃料材であるペレットの購入時期も、考え始めなければならないのだ。
そして更に今年は今回のブラックアウトを教訓にした自家発電機の購入時期も、真剣に検討しなければ成らない。
北電の人災によって引き起こされた先のブラックアウトは、9月の上旬であればまだ許されるが本格的な冬季に同じことが起こるとなれば、命の危険に直結するからである。
私の住んでる南十勝は根雪が積もる12月~2月ごろは、最低気温が-20度前後に成ることはざらだからだ。
因みに我が家の暖房は、床暖とペレットストーブとによって構成されている。
純粋な薪を使った暖炉ならその手の心配はないのだろうが、電動でペレットを供給する仕組みのペレットストーブも、灯油をボイラーで燃やし続ける床暖も電気の供給が止まると、自動的に運転が停止するのだ。
電力の供給停止が命にかかわるという表現は、北海道の冬季においては決して大げさな表現では無いのである。
以上のようなことがあるから、我が家では自家発電機の購入はすでに決定事項となっている。しかし、その購入時期についてはまだ決めていない。
秋分の日が過ぎ、寒さの到来を意識しつつ、これから少しずつ冬バージョンのライフスタイルを準備して行かなくてはならないのである。
それにつけても、ブラックアウトが9月初めのことで冬季に起らなかったことは、ホントに不幸中の幸いなのだ。
北電という、電気事業者としての経営者能力の低い企業の、ほぼ独占的状況下の社会で生き抜いていくためには、私たちも自分でできることはやって行かなくてはならないのである。
北海道で生きていく、という事にはそのようなある種の覚悟も必要である。
厳しい自然環境下では、自助努力は必須にして欠くべからざる基本課題である。北海道にある種の憧憬を抱いている方には、その事をしっかり気付いてほしいと思っている。
北海道には「セイコーマート」というご当地コンビニがある。
北海道を中心に1,000店以上の店を展開している、ローカルでユニークなコンビニである。首都圏の大手コンビニなどに慣れている身には、ちょっとローカルなある種あか抜けない印象を持ったりするコンビニなのだが、最近の新しい店舗などでは全国チェーンと比べても引けを取らないクオリティに成ってきている印象を受ける。
その道産子コンビニが今回の大地震で、株を上げている。
というのは道内に1,000店以上ある店舗の殆どが、今回の全道停電=ブラックアウトという緊急事態の中で24時間営業をしていた、というからである。
その秘密は、このコンビニは非常事態に備えすべての店に自家発電のための発電機を備えており、停電に成っても照明を切らすことなく営業可能に成っているのだという。
又レジなども通常は本部とオンラインで繋がっているのだが、非常時には単独の店舗でもレジが機能するようなタイプのレジを使っているのだ、という。
要するに、停電を含む非常時対応が店舗経営の仕組みとして確立されているのである。
そのようなビジネススタイルが確立されているから、今回のような全道がブラックアウトするような事態に成っても、しっかり店舗が機能していたのである。
この道産子コンビニが地元で評判に成っているのは言うまでもない。一部のSNSなどでは「神対応のコンビニ」などと評されているようだ。
「備えあれば憂いなし」をまさに地で行ってるコンビニなのである。
セイコーマートがなぜこのようなビジネスシステムを構築しているかというと、一つは冬季における降雪による孤立化への備えであるという。さらには7年前の東日本大震災や2年ほど前の台風被害を教訓としたからだ、という。
企業として真剣に、まじめに自然災害やシビアな自然環境に向き合って来たからである、というわけだ。
云うまでもなく、今回の道産子コンビニの対応は拍手喝さいに値する。この会社の経営陣に私は信頼感を抱いた。
そして多くの道産子たちはこの「セイコーマート」という身近なコンビニに対する信頼感を、高めたことであろう。
と同時に身近なところにこのコンビニがある事を喜び、誇りにも思っている事であろう。
企業に対する信頼感というのは、このような非常時の対応によってまた高まったり低く成ったり、喪失したりするのである。
今回の道産子コンビニのビジネスシステムを見て、同じ自然環境で事業活動をしていながら、道産子コンビニと北海道の電力会社の経営陣との危機管理に対する姿勢や、経営者のガバナンス能力に大きな違いがある事を、強く感じている今日この頃である。
今回北海道全域(全道)が停電に成ったことの最大の原因は、北海道電力経営陣の企業経営者としての判断の甘さにあり、同時にそれを看過してきた経産省や北海道庁の行政指導の不十分さにある、と私は思っている。
北海道は言うまでもなく広大な地域であり、全国一の面積を持つ。九州と比較してみるとその事が好く判る。
北海道の面積: 約83,453k㎡
九州全域の面積:約44,436(約53%)
中国地方の面積:約31,913(約38%)
九州+中国地方= 約76,349k㎡(約91%)
上記のように北海道の面積は「九州+中国地方」連合よりさらに10%程度広いのである。
人口自体は、兵庫県の人口にほぼ近く530万人程度である。
今回の停電の原因は、停止中の泊原発に加え道内5つの主力火力発電所が地震による緊急停止をしたことが原因である。
そして不幸なことに今回の震源地である厚真町に最も近かったのが、主力の発電所である「苫東厚真火力発電所」(165万kw:44%のシェア*)なのであった。
震源地からの距離は10km程度であったという。
因みにその主力発電所とは
・苫東厚真火力発電所
・伊達火力発電所
・知内火力発電所(『大野土佐日記』舞台)
・奈井江火力発電所
・砂川火力発電所 *地震前日の380万kwを基準にした場合のシェア
の五か所である。
私がこれらの発電所を問題にするのは、その位置である。上記五か所の主力発電所はいずれも北海道の西半分にしか存在しないのである。
広大な面積を持つ北海道は大きくは二つの山脈や山系によって分けることが出来る。
ほぼ中央に在って、北海道を東西に分割するのが日高山脈である。
・日高山脈の西側;道央/道南/道北の半分程度といわれるエリアで大都市札幌や
函館/苫小牧/小樽を擁するエリアである。人口が最も多く、企業活動が最も
活発なエリアである。
・日高山脈の東側:道東/道北の残り半分エリアで、帯広/釧路/北見・網走/根室
/知床と言った街がその代表である。人口密度は低く第一次産業を主体とした
エリアである。
このエリアは更に、中央やや上に在る大雪山系によってオホーツク海側(北側)
と太平洋側(南側)とに分かれる。
従って日高山脈の西側半分に集中している五つの発電所が震災被害を受けると、東側半分の太平洋側もオホーツク海側も全部影響を受けるのである。距離に関係なくである。
私が北海道電力の経営陣及び経産省/道庁の行政指導の甘さを指摘するのは、目の前の経済効率だけを重視し、北海道全体での電力事業経営の視点やガバナンスが欠如しているからである。
危機管理に対する認識が欠如し、オルタナティブ(並行的)な選択肢を用意していない点こそが問題なのである。
地震大国日本列島で生きてく以上、地震は避けて通れないのである。
7年前には「東日本大地震」2年ほど前には「熊本地震」今年は「大阪北部地震」そして「北海道胆振東部地震」である。
参考にすべき事例は枚挙にいとまない。しかし彼らはそれ等から何も学んでいないのではないかと、私には思えるのだ。
偶然のことだが地震の起きた日の近く、私が購読する新聞のコラムに「足並みそろえると全滅する・・」という植物学者の見識を紹介していたが、まさにその通りなのである。
今回の震災の被害者、全道民約300万世帯/530万人は多くのことを学んだと思う。
選択肢が一つしかない環境では、その唯一の選択肢がコケたら全道民と沢山の家畜たちは、一斉に運命を同じくしなければならない、全滅してしまうという事をである。
幸いなことに先般、電気事業者法が改正されたことにより「発電事業者」と「送電事業者」「売電/小売事業者」とが分割されたようだ。
日高山脈西側の発電事業者が、オルタナティブな選択肢を提示する事が無いままであれば、日高山脈東側の道民や事業者の少なからぬ個人や法人は、自らの生活と経済活動の自衛策として、新たな発電事業者の選択を検討し始めることに成るであろう。
伝統的に官営の移民政策で入道して来た道央/道南の屯田兵の末裔に比べ、道東や道北のエリアに入道して来たのは依田勉三達の末裔で、自主自立意識が高い人達なのである。他者への過度の依存はしない人種が多いのだ。
今日、やっと電気が通じた。
地震発生から殆ど48時間ぶりといって良い、丸二日である。
尤も大樹の市街地では昨日の早朝には通電が開始したというから、市街地から12・3kmは離れている、この海岸近くの集落いわゆる郡部といわれるエリアとは、タイムラグがほぼ一日あったというわけである。
ラジオなどの報道では昨日の午前中には全道の40%、昨日中には80%が回復するだろうという事であるから、遅くとも昨日の夕方ごろまでには南十勝の我が家も、回復するのではないかと、楽観的に考えていた。
ところが実際に通電したのは本日の未明であった。という事は我が家の在るいわゆる郡部は、全道の中の残りの20%に該当するのだ、という事が判った。
今後はこの種の報道があった場合は、常にこの現実を頭の片隅において行動する事が必要になる。すなわち停電やその他のライフラインに対する備えにおいて、である。
その事を今回の経験から私達家族は学んだ。
電気が通じなくなって一番困ったことは他者とのコミュニケーション手段であるスマホやケータイが使えないことである。
TVなどの報道を見た親戚や友人たちから電話やメールが来るのだが、それへの返信が出来ないのだ。
しかも今回の体験で判ったのは、通信網が停止しているとスマホの消費スピードが一気に進むことであった。普段はこのエリアでは3Gで通信しているのであるが、大地震の後の通信網が機能していない時においては、1kという表示であった。
受信しようにも発信しようにもそれを受けてくれるアンテナ(基地局?)が、機能していないから電波が通常以上の出力をして、その受発信先を探し求めて彷徨い著しく消耗しているのであった。
その事に気づいてから私達は、スマホやケータイの電源を切ることにした。非常時には非常時の対応が必要だからだ。
でないとホントに連絡が必要な事態に成った時に、緊急連絡が出来なくなるからである。
この南十勝では今回の地震で影響があったのは、電気だけで水道やガス・道路などのインフラは全く影響がなかった。震度は4であったし震源地の胆振(いぶり)東部とは150~200㎞は離れているからである。不幸中の幸いなのであった。
しかしそうは言っても、街中がほとんど暗闇に包まれ、信号機は1/4ぐらいしか機能していなかった。おかげでこの二日間は非日常空間を体験した。
実は私は地震の真っ最中は新潟の上越市に次回作の取材に訪れており、家人のメールで停電以外は影響がない事を知り、ニュースは観たがそんなに心配はしていなかった。
その日の夕方の便で帯広空港に帰ることに成っていたのだ。
幸い帯広空港は通常通り機能しており、航空機の運航もスケジュール通りであった。
従って、北海道電力が言う全道の停電という情報に関しても、高をくくっていた。私が到着する18時半ごろにはある程度回復しているのではないかと、甘い見通しを立てていたのであった。しかし、現実には停電は48時間続いた。
今回の事態は北海道電力の引き起こした問題であると、私は思っている。九州よりも広い面積の北海道の中央部で大地震が起きたからと言って、北海道全域が同時に停電に成る、という事はその発電および通電システムに、欠陥があるからだと私は思っているのだ。
その件について次回にたっぷりと触れたいと思っている。
今日はとにかく久し振りにPCが使えるようになって安心しており、同時に嬉しく思っている。取材旅行期間を含めて1週間以上PCに触れていなかったからである。
昨日あたりから台風20号と19号とが日本海に抜けた後、北東に向かい北海道に接近するという予報があった。
二年ほど前に台風が北海道を直撃した事があって、今回も多少気にはしていたがコースの関係で前回のような大きな被害をもたらすには至ってない。ラッキーだったのだろう。
いずれも北海道に上陸する前に温帯低気圧に成って、それなりの雨はもたらしたし、強風も伴ってはいたようだが大きな被害は起こっていない。
元来北海道と台風は縁遠い関係にある。それは海水温が影響しているからである。気象情報でもよく言われる様に台風のエネルギー源は、温かい海水温である。27度が分水嶺に成るようだ。
今年の北海道は夏とはいっても20~25度の日が多く、30度を超える日は数回あったかどうかだし、真夏日を経験する事があまりなかった。したがって海水温もまた低く27度などは、夢のまた夢といった感じであった。
そう言った事を考えれば北東北辺りに台風がやってきても、今年は勢いが減速し台風→熱帯低気圧→温帯低気圧と変わって行くことはある程度予測はできたのかもしれない。
通常、台風が熱帯低気圧に変わることはあっても温帯低気圧まで低温化することはあまり無かったと思うが、今年は温帯低気圧にまで下がっている。それだけ海水温が低いことを物語っているのだろう。
生活する分には今年の夏は過ごし易かったのであるが、野菜などを作っている農家には日照不足という事で、作物の生育には少なからぬ影響があるようだ。ニュースなどの報道では例年より成長のスピードが1週間ほど遅れ気味である、という。
自然環境ばかりは、どうしようもない。人間は環境と共に生きて行かねばならない生物なのだ。もちろん他の生物も同様であるが・・。
現在の地球温暖化という現実は、人類の産業革命以来の生産活動がもたらしたものであることを考えれば、現在および将来の自然環境のありようを人類は自らの意志と努力によって、方向付ける事はできるであろう。温暖化対策である。
アメリカや中国・インドといったCO2排出大国がこの現実にまともに取り組もうとしない限り、温暖化の流れを止めることは難しいであろう。
中国やインドは最近大気汚染が激しく成っている事もあって、温暖化対策にも目が行き始めているようである。したがって遠からず大気汚染対策は練られるであろう。
問題は、自分の選挙民のことしか考えていないアメリカの花札大統領である。
目先の利益や自分のことしか考えていない人物が大国のリーダーであり、またそれを支持する人たちが一定数居るという現実は、不幸な事である。
今年の11月にアメリカでは連邦議員の中間選挙があるという。この選挙結果の如何によっては、今後数年間の温暖化の方向性は少なからぬ影響を被ることに成るであろう。
選挙自体は他国のことではあるが太平洋の対岸に住んでいる私達も、地球の近い将来に影響を与える国の政治動向を、注意して観て行かなくてはならないだろう。
昨日私は息子を帯広空港まで送って行った。
長い夏休みを涼しい北海道十勝で過ごしたあと彼は、まだ残暑の残る首都圏にと戻って行ったのであった。
その息子の希望で昨日は最後に帯広でお寿司を食べた。
息子が北海道の寿司を好んで食べるようになったのは、首都圏で暮らすように成ってからのことである。
それまでは私が長期出張から帰って来た時に、ほとんど必ず空港帰りにすし屋に誘っても必ずしも積極的ではなかった。
やはり首都圏で暮らすようになって、北海道の豊かな食材で食べるお寿司の旨さに、彼も気が付いたようだ。
私が出張の際に神奈川の息子の宿に寄るようになり一緒に外食をすることがあるが、その際お寿司を食べる度に彼は感じているようだ。北海道の寿司は旨かった、と。
私が北海道でお寿司を食べて、その食材の豊富さや一つ一つの具材の大きさ、更に実の充実さを感じるようになったのは、30代の頃に仕事で札幌に来るようになってからである。
ボタンエビを食べた時に、北海道で甘えびといえばこれです。と板前に言われて食べさせられた時であった。
実際にはボタンエビと甘えびは違うが、本州から始めて北海道に来た人間を彼はそう言ってからからかったのだと思う。
その後私は何度か公私にわたって北海道を訪れるようになったが、今でも一番感動し記憶に残っている食材がある。
ズワイガニである。すすき野の鮨専門店で食べたそのズワイガニの脚(太もも?)は、10cmくらいはあった。大きくて実の詰まったカニの脚であった。
ほのかに甘くて食べ応えもあった。上品な味であった。
何よりもズワイカニの脚でそこまで大きいのを食べたことが無かった。本州や北陸においてもだ。やはりカニ本体の大きさが違うのである。
北海道の魚類は総じて体が大きく、身が引き締まっている。厳しい自然環境がそのように育てるのであろう。
十勝の太平洋側ではもちろんカニも採れるのであるが、やはり貝類が旨いように思う。ホタテやツブ貝をこちらで食べた後本州で食べても、比べ物にならないのである。
私の記憶に残るズワイガニの脚を食べたのは、確か10月ころではなかったかと思うが、秋から冬に成ると北海道ではおいしい食材が海からも畑からも採れる。
いよいよおいしい季節の始まりである。北海道に住んでいる悦びを堪能しようとおもう。
今日はお盆明けの初めての月曜日であるが、北海道では今日から二学期が始まるところが多いようだ。北海道の夏休みは本州と比べて明らかに少ない。確か25日前後だったと記憶している。その理由は冬休みが長い事の裏返しである。
本州の夏休みが概ね40日前後あることからその差の15日2週間ほどが北海道では、冬休みに回るのである。
従って北海道の冬休みは本州より2週間近く長く、夏休みと同じくらい続く。スタートは本州と殆ど変わらないでクリスマス前後に始まり、冬休みが終わるのが1月の18日前後であったかと思う。
今年の北海道十勝地方は20度前後の日がずっと続いており、例年だと30度近い日が1週間程度は続くのだがそれもなく、晴天の日も多くは無かった。したがって首都圏を始めとした本州のうだるような暑さとは全く無縁で、過ごし易い夏であった。と同時に一抹の物足りなさを感じてもいた。
その天候は精神的な物足りなさばかりではなく、十勝の主要産業である農業にも少なからぬ影響を与えているようであった。雨は適度に降っていたが太陽の日照が十分ではなかったからだ。報道などによると通常より7日程度発育が遅れている、らしい。
家人もビニールハウスで野菜などを栽培しているのであるが、同様のことを嘆いていた。
しかしここ数日晴天が続き、今日などは30度に迫る気温に成るらしい。十勝のアグリカルチャー従事者は喜んでいるに違いない。が子供達には少しばかり遅すぎた夏かもしれない。
お盆が過ぎ、夏休みが終わると素早く秋がやってくる。それは朝夕の気温低下から始まる。
まだ暖房を入れるほどではないが、頭の片隅でそういったことも考え始めるのである。実際には9月下旬か10月上旬から早朝の暖房は始まることに成ろうかと思う。
そしていよいよ秋味の季節に成る。ここでいう秋味とは鮭のことであり鮭が産卵に向けて太平洋辺りから故郷の清流を目指してやってくるのだ。太古以来続く北海道の風物詩である。それに伴い太平洋沿岸の漁港は活性化し、漁師たちが一年で一番忙しい時期を迎える。実りの秋である。
終戦記念日、または配線記念日 2018.08.16 |
昨日は8月15日で、終戦記念日であり同時にまた敗戦記念日であった。
第二次大戦が終わって73年目に成る、という事だ。
先の大戦では、日本人だけでも3百4・50万人が犠牲に成ったという。その中には戦地に赴き日本の当時の権益を確保するための犠牲に成った兵士はもちろんの事、国内に居て空襲や原爆で犠牲に成った多くの国民も含まれている。
戦没者慰霊式などを見ていると、この先の大戦の犠牲者たちに一番敬意を払っているのは天皇皇后の皇室のメンバーであるように思われる。
一方で政治家たちの発言は軽く、口先だけで気持ちが伴わないと感じられる。
戦争という行為は、戦地に向かった日本人はもちろん戦地で日本兵と戦った相手との戦闘行為である以上、相手の国の兵士や民間人にも犠牲が出る。当然のことだ。
自分たちは主人公かもしれないが当然敵役も存在するのだ。そしてその敵役にはその地においての歴史や伝統・文化があり、共同体があり家族もまたいる。
日本の権益を確保する、追及するという事は同時にそれまでの権益を持っていた人達からそれらを奪う事を意味するから、衝突することに成る。当たり前のことである。
その過程において当然犠牲者が出るのであるが、それは攻撃する側はもちろん攻撃される側にもである。それを侵略行為という。
これは日本だけが行って来た行為ではなく有史以来、世界中で続けられてきたことである。
しかしだからといって、日本が行って来た事を単純に正当化することはできないのも確かだろう。
その当然のことに対して日本のいわゆる保守勢力という人々は、なかなか認めようとしない傾向があるようだ。
これは第二次大戦が終結して以来ずっと続いているように思われる。
自分たちに都合の悪い事や、認めたくないことを真摯に受け止めようとしない姿勢である。
私はそういうスタンスを受け入れない。事実を事実として受け入れようとしない人間を一人の人間として、高く評価する事がない。そのような人達にインテリジェンスを感じないし、洞察力も足りないと思う。同時に厚顔無恥な人種と感じる。
第二次世界大戦で3百4・50万人が犠牲に成ったことは、とても痛ましい事だと思うし同じ過ちは繰り返してはいけないと、心からそう思う。
それは日本人にとってももちろんであるが、その日本人の行為によって犠牲に成った国々の人々のためにも、である。何十万人か何百万人かは判らないが、同様に犠牲に成っている人々は侵略先には存在するのである。
私はこの愚かな行為が明治維新以来の富国強兵策のとどのつまりだったと思っている。
そして明治維新以来7・80年間続いた軍国主義体制・天皇制体制が崩壊した事はほんとに好かったと、思っている。
それはイデオロギーの問題というより、軍事優先の全体主義国家や個人崇拝の国家体制が崩壊したからである。
現在でもなお社会主義や共産主義を標榜する一部の国々にみられる様に、個人の権利や福祉より、個人崇拝や自分たちが所属する政治体制の維持を優先するような社会が存在する。
私はそのような国家には暮らしたく無いと思っているし、私のような個人主義者・民主主義者はきっと暮らしていけないだろうと思うからである。
これは政治イデオロギーの問題であるとともに宗教イデオロギー、すなわち宗教過激派が支配する国においても同様である。
終戦記念日はまた同時に、明治維新以降の軍事優先体制の崩壊及び天皇制の個人崇拝を終わらせた敗戦記念日でもある。
隣国の北朝鮮や中国を横目で見ていて、そのことを喜んでいる私である。
今日はお盆の最中である。
お盆というのは言うまでもなくお正月とともに、日本人にとってはとても重要な行事である。そのような共通認識があるから人々はお正月とともにお盆に合わせて長期休暇を取り、故郷に行ったり、バカンスをとったりすることが出来るし、それを許されもする。
若いころはそのような年中行事にはあまり関わらず、バカンスを中心にとることが多かった。公然と長期休暇が取れることは大きなアドバンテージであったからだ。
しかし40前後に成って近親者の死という、あまり望まないイベントがやってくると死者を悼むといった事がとても大きな意味を持ってくるようになった。
とりわけ自分にとって大切な人の存在がなくなる事は少なからぬ心の痛みを伴うものである。両親であれ、お世話に成った親戚であれ、親友といっても良い友の早すぎる死であったりする。
そんな時死者を悼み、死者を訪ね、死者に想いを馳せるといった行為が大きな意味を持ってくるのである。
日常生活の忙しさにかまけて、普段は棚上げしていた人々を想い、リスペクトするのだ。
そして同時に現在の自分のことを見つめ直すきっかけにも成る。
私はこのまま今の仕事を続けていて好いのだろうか、自分の時間を人生をこのまま費やしていてよいのだろうか、こんな時親父はどうしただろうかとか友人はどうしただろうか、といった事を考えるのである。
もちろんそのような沈思黙考の機会があったとしても、現実は待っているから大きな軌道修正などは図れない。家族を養わずにはいられないし、会社での仕事も待っている。
しかしそういったことを考える良い機会であることは間違いない。
私たちにとって、お盆という行事は死者との対話を通じて、もう一度自分自身を見つめなおす良い機会なのである。
故郷を訪ね、旧友と交わり、墓を訪ね死者との対話を通じて、自分の来し方行く末をおもんばかるのである。
貴重な時間を有効に使う事が出来る大切な行事なのである。
俳優の津川雅彦が先週亡くなったというニュースが入ってきた。
妻の朝丘雪路が4月に亡くなっていて、4か月後という事に成る。
彼の俳優としての魅力を私は少なからず感じていたので、残念である。
俳優や歌手なんかもそうだが年齢とともに魅力を増していくタイプと、逆に輝きを失っていくタイプがあるが彼の場合は前者であった。
若いころはグッドルッキングで美男子俳優であったが、俳優としての魅力は殆ど無かった。
しかし伊丹十三の映画に準主役で出るころから俳優として一皮むけたようで、存在感が感じられ味が出てきた。上手に年齢を重ねてきたようだった。
もちろんその成長の過程においては人に言えない苦労や苦悩もあったに違いないし、少なからぬ挫折も経験したのかもしれない。本人のみが知ることだ。
しかし結果的に彼は俳優として歳を重ねてから、明らかに魅力を増していった。「相棒」での法務大臣役辺りからは、ほんとによい味がにじみ出ていた。
「風雪の当たるとこほど樹は育つ」というが彼もまた少なからぬ風雪に見舞われてきたのであろう。あと十年は彼の味のある仕事を見ていたいと思っていたのでとても残念である。
ご冥福を祈る。
さてその津川雅彦氏であるが、妻の朝丘雪路が亡くなってから4か月足らずで後を追う様に亡くなっている。このことに私は少なからぬ感銘を受けている。
かなり前から両者が相思相愛であり、仲の良い夫婦であると言われ実際にそうであったようだ。いわゆる「オシドリ夫婦」として有名だったと思う。
そしてその仲の良さが妻の4か月後の彼の死によって、改めて証明された気がするのだ。
ホントに仲の良い関係というのは片方がこの世に存在しなくなった時に、身体の一部が欠落したように成ってしまうのではないかと、思うからだ。それもとても大事な部分が・・。
もちろんそれは心の問題として発生してくるのだと想う。
津川雅彦氏にとって朝丘雪路という存在はきっとそのような不可欠な存在だったのではないかと思われる。自分の命に影響するほどの大きな存在だったという事であろうか・・。
思えば兄の長門裕之もまた、妻の南田洋子が亡くなって1年程度で後を追う様に亡くなったかと思う。
兄弟して妻想いの人間だったのだろう。
二人はきっと愛情の豊かな家庭で育ってきたのであろう。そして彼らを育てたご両親もまた夫婦仲がよく家庭が円満だったのかもしれない・・。
ご冥福を祈る。
今週から私は仕事で首都圏に来ている。
月に一度の定例会議に出席するためである。
で、連日の酷暑に遭遇している。
先週あたりの台風が来る前も相当暑かったらしいが、今週もまた暑い。
今日も体温を超えるくらいの暑さに成る、との事だ・・。
私と入れ替えに息子は北海道に、夏休みで帰った。
やはり彼にもこの暑さは相当堪えるらしく、喜び勇んで北海道に向かった。
私は厳しい暑さと厳しい寒さとを比べて、どちらの生活を選ぶかと聞かれたら、間違いなく寒い方を選ぶ。
冬の寒さには耐えることが出来ても、夏の暑さには耐えられないのだ。
特に梅雨の後半あたりの蒸し暑さが始まる、7月上旬頃から首都圏を脱出したいとずっと考えて暮らして来た。従って夏休みは毎年7月下旬から8月上旬を中心に取って来た。サラリーマン時代の事である。
その様に過ごしてきた私は、50歳前後の頃から北海道移住を真剣に考えだした。
TV番組では「移住者の番組」や「田舎暮らしの番組」を家人と一緒に、良く観た。
家人の気持ちも私とあまり変わらないことを確認してから、夏休みの先を北海道にと定めるようになった。
毎年この時期に成ると家族で北海道を目指した。
回を重ねるたびに、十勝地方が良いのではないかと思うようになった。
やはり宏大な十勝平野は魅力であった。
最も北海道らしい、イメージに近い場所でもあった。
それから幾つかの選択条件を基に絞ったのが南十勝である。
その後のプロセスは下記の通りであった。
1.南十勝の市町村役場を尋ね、移住者の窓口担当者と接触した。
2.五・六カ所の自治体を回り、熱心で親切な担当者のいる町を選んだ。
3.彼が案内してくれる移住先候補を何ヶ所か見て廻った。
4.その中で気に入った候補先を絞り、家人を連れて来て意思決定に参加させた。
といったプロセスを5年ほどかけて積んできた。
そしてほぼ移住先を絞った後、今度は極寒の冬休みを体験しに来た。
夏の過ごしやすい時季を4・5回経た後で、最後に年末からの厳しい冬の1週間を体験したのだ。
移住してからひっくり返ることが無いように、敢て厳しい冬を体験したのである。
その年末年始の期間に運良くというか運悪くというか、大雪が降った。
TVの全国版のニュースでも大樹町の大雪が話題に成ったほどであった。
一晩で5・60cmの大雪を体験したのである。
朝に成って玄関を出ようとしたら、屋根の雪が落ちていて150・60cmの積雪が借家の玄関に立ちはだかったのである。
小学生だった息子と二人で、スコップを使って雪のトンネルを造って無事に脱出することが出来た。我が家では今でも語り草に成っている。
やはり移住を考える場合は、過ごしやすい夏と共に厳しい時季、過ごしずらい時季をも体験しないとだめだと思う。
コインの表と共に裏もしっかり見なくてはならないのだ。
その上で覚悟をもって、移住を選ぶのである。途中で安易に撤退しないためにも・・。
この暑い本州で過ごしている方々の中で、北海道辺りに脱出や移住を検討されている方は参考にしてみてください。
4月から11月中旬まで北海道は、天国ですよ。
もちろん残りの5か月は、厳しい冬が待ってますけどね。
夏は牧草の繁る畑地の「冬景色」
世間が夏休みに入る頃に成ると郷里の友人や親戚からお中元が届く。
私は高校生までの18年間を山梨で育った。
私の通った高校は現在南アルプス市と呼ばれる地域で、昔から果樹の栽培が盛んである。
当時から季節に成ると、サクランボやスモモ、白桃といったものを友人や親戚からもらったりして、おすそ分けにあずかっている。
若い頃はあまり友人や親戚とは連絡を取っていなかったが、40過ぎた頃から彼らとも連絡を取ることが多くなった。
若い頃は自分が生きる事に精いっぱいで、昔からの古い付き合いにはあまり目が行かなかったこともあったし、両親も健在で私が前面に出る事も無かった。
40を過ぎて厄年などのイベントで会う機会があったり、親が他界するなどして旧交を温め合ったり、親戚との付き合いを始めたりするようになった。
それから彼らとお中元やお歳暮をやり取りするように成ったのだ。
そのおかげで、懐かしい故郷の味覚を堪能することが出来るように成った。
友人や親戚が送ってくれるスモモや白桃は、甘くて固くて旨い。
子供の頃から採れたての果実を食べ慣れている身には、スーパーなどで売っているスモモや白桃・ブドウはとても食べられない。
甘みが全然違うし、変に柔らかかったりするのだ。
まだ青みが残るうちに採り、流通過程で色付けさせるような商品は、必然的に甘みが足りないのだ。
これは果物に限ったことではなく、トマトやキュウリ・ナスといった野菜でも同じである。
自家栽培している野菜に比べてスーパーや八百屋で買う野菜が、旨くないのと同じであろう。原因は木成りで完熟させたかどうか、が分かれ目に成っているのである。自家野菜がそうであるように・・。
友人や親戚が送ってくれる果樹類は、やはり木成りの完熟モノなのである。
彼らも友人や親戚に送るものと農協に出荷するものでは商品を選別しているのだ。
木成り完熟の自家製果樹を送ってくれるから、旨いのである。
私はそれらの果実を食べる度に山梨に友人や親戚がいて好かったと、感謝している。
その感謝の返礼は、私の方から送る地元の品々である。
かつて千葉の東葛地域に住んでいた頃はもっぱら梨が中心であったが、北海道に移ってからはこちらの海産物に成っている。
料理が好きな人たちには昆布などを中心に送ることが多く、酒飲みには魚介類の珍味である。どちらでもない場合は毛ガニや鮭を送っている。
私の返礼は本州の海のない県の彼らに感謝されることが多い。したがって現在我々は良好な関係を築いている。
そのお中元の中で私が気に入っているのは、スモモの「貴陽」である。
同じスモモでもソルダムやプラムといった品種は大味で、旨さを感じることが少ない。
それらに比べは「貴陽」は、貴品があって味も濃くおいしいのだ。
「貴陽」とは良く名付けたものである。名が体を現しているのである。
「貴陽」自体はスーパーなどで購入することも出来るが、やはり木成り完熟の「貴陽」とは味のレベルが合う。産地から直接求めることのできる「貴陽」にはかなわない。
私の様に山梨に友人知人がいない方は、山梨に行く機会があった時に是非「産地の味」を味わっていただきたいものである。本物の味を、である。
そしてそれをキッカケにして、そこから新しい人間関係を築くことが出来れば、新しい歓びが始まるかもしれないのだ。
「求めよされば与えられん」なのである。私は幸運を祈って止まない。
「貴陽」と石楠花
今日は今年の土用の丑の日、という事らしい。
土用の丑の日といえば思い出すのは、やはりウナギであろう。
ここ数日来の本州の厳しい暑さの中で暮らしていれば、ウナギを食べたくなるのはよく理解できる。
私自身本州に居た時はこの時期に成ると、頻くウナギを食べに行っていたものだ。
私が贔屓にしていたウナギの店は、千葉県の利根川沿いに在る川魚を料理してる店である。
坂東太郎と称された利根川は言うまでもなく、関東平野を縦断する大河で、またよく氾濫する暴れ川であった。
その利根川の下流、太平洋まではあと10~15kmという距離にその店は在る。
千葉県栄町安食地区がその場所である。
安食は名前からして食べ物に縁のある町であるが、その店は利根川から200mとは離れていない場所に在る。
私がその店を知ったのは今から30年近く前のことである。知り合いの人に連れて行ってもらったのである。
その店のウナギは旨かった。大きさもそれなりにではあるが身が締まっていて歯ごたえも良かった。タレも私の好みに合っていたのだが、とにかく美味かった。
東京の街なか辺りで食べる、妙に柔らかくて歯ごたえのないウナギとは明らかに違っていた。
私にとってのウナギの味は、子供の頃父親に連れられて行ったJR身延駅近辺の富士川沿いにあった和食の店で食べたそれが、基準に成っていた。
今から50年近く昔のことだから、多分天然ウナギを食べていたのだと思う。いけすに入っていたウナギの腹が黄色かったことを覚えている。
回数自体はそう多くはなかったが、いずれにしてもその時食べたウナギが私にとっては基準であった。
で、その安食の店で食べたウナギの味は、まさにその店で学んだ基準に合格していたのだ。
それ以来私がウナギを食べに行く先は、その店に決まってしまった。
たまに職場の近くに在った築地でもウナギの店として有名な店で食べることがあったが、残念ながらその著名な店のウナギは私の基準には合っていなかった。
柔らかくて歯ごたえの無いウナギは養殖ウナギだと推察され、ほとんど利用することが無かった。
そして今私は北海道に居る。
北海道に来てからは土用の丑の日は全くと言ってよいほど、縁が遠くなっている。
初夏を思わせるこの地の気候では、身体がウナギを欲しないのである。
やはり気温が35度以上無いと、敢えてウナギを食べようという気には成らないのだ。これもまた自然の摂理であろうか・・。
灼熱の本州に居て、ウナギをうまく食べる喜びを味わい続ける事よりも、冬は極寒であるが夏は初夏の気候であるこの北海道の南十勝で、ウナギを敢えて食べたいと思わない生活を選ぶかの二者択一を迫られるとすれば、迷うことなく後者を選ぶ私である。
そんな私が次にウナギを食べたくなるのは、いったいいつに成るのだろうか・・。
大きなシジミ貝、made in taiki 2018.07.18 |
この時期私の住んでる大樹町のスーパーに行くと、サイズの大きなシジミ貝に遭遇する。
一見するとアサリかと見まごうサイズだが、「やまとシジミ」という事だ。
このやまとシジミは宍道湖などで採れる小粒なのが有名で、普通に私たちが馴染んでいるのは1~1.5cmといった大きさだと思う。
ところが下の写真の様に、大樹で採れるやまとシジミはその倍近くはある。大きさに厚みを加味すると体積的には、一般的なシジミの4倍近くに成るのではないかと思う。
従って、ちょっと見はアサリの大きさなのだ。さすがにハマグリ大とは言わないが初めて見ると、やはりビックリ⁉するのだ。
因みに下の写真で言えば茶色っぽくて正面右手に在るのが「アサリ」で、
向かって左手の真っ黒いのが大樹の「やまとシジミ」なのだ。
私の驚きが、決して大げさではないことは一目瞭然だと思う。
この大きなやまとシジミには、実は私は以前にも遭遇している。
14・5年前のことだが青森の津軽半島を旅行していた時に「十三湖」の宿で遭遇していて、私には免疫があるのだった。
ただ、本州でも津軽半島の十三湖ぐらいしか採れないという事を知っていたから、大樹でも採れる事を知って驚くと共に、ひそかに喜んだのであった。
因みに、この大きなシジミのお味はどうかというと、やっぱりシジミはシジミなのだ。
残念なことに、大きいからと言ってアサリやハマグリのような貝自体の甘みや味は、殆どしない。
淡白で、あっさりした味である。
値段は10粒程度で5百円前後だから、決してリーズナブルというわけではない。
従って、珍しい食べ物として数回味わってしまえば、次回からはあまり手が出ない代物なのだ。少なくとも我が家の家人はそう思っているようだ。
尚、この大きなやまとシジミは、大樹でも太平洋に面した晩成温泉近くの「ホロヤカントー」という淡水湖だけで採れる、という事である。
知り合いの漁師が言っていた。彼はこのシジミの漁業権を持っているからその情報に間違いはない、と思う。
いつか大樹に来て晩成温泉に寄る機会があったなら、隣接するこの淡水湖を訪れるとよいかもしれない。
7月の上旬から中旬にかけてであれば、この大きなやまとシジミに遭遇することが出来るかもしれないのだ。
ついでながら、例の宇宙ロケットMOMOの打ち上げ場所は、この晩成温泉&ホロヤカントーからそう離れていないので
「ロケット場観光」「晩成温泉」のついでにこの淡水湖に立ち寄るのも良いかもしれない。
この大きなやまとシジミは 大樹町の初夏の風物詩でもあるのだ。
今の時期の十勝南部は、本州の猛暑をしり目にいまだに初夏といった感じで最高気温が20~25度といった過ごしやすい時節である。
避暑地の候補の一つとして、検討に値するかもしれない。
毎年この時期に成ると、日本列島のどこかで集中豪雨が発生し、多くの犠牲者が出る。
去年は福岡県の筑豊エリアを中心に発生し、今年は瀬戸内海を挟んだ中国地方南部と四国北部とに集中豪雨が発生して、多くの方が犠牲に成っている。
今年は200人を超える方が亡くなっており、安否不明者もまだ4・50人はおられるようだ。痛ましいことである。
亡くなられた方や行方不明の方々にはそれぞれの家族があり、様々な人生があることを思い、その喪失感や哀しみの大きさを想うと、ほんとに痛ましいことだと思う。
また犠牲に成られた方々の、その瞬間のエピソードが報道などで克明に知らされるにつき、犠牲者の無念さに心が乱れます。
改めて犠牲に成られた方々の、ご冥福をお祈りします。 合掌
実は私自身小学校6年生の秋に台風の影響で、裏山の土砂が崩れ住んでいた家が数mほど流されたという体験をしています。今から半世紀ほど前の話ですが・・。
その時は裏山の異変に気が付いた父親の誘導で、早めに知人宅に避難し土砂崩れの瞬間は経験していませんが、もしそれを体験していたら今でもトラウマに成っていたかもしれません。
私は今回の河川の氾濫や山崩れの映像を見ていて、田子の浦の海辺の小さな公園に祀られていた「阿字と竜神様」を祀った神社(阿字神社里宮)の事を思い出しました。
古代から中世の人々はこの自然災害の源が、集中豪雨や台風といった自然災害によるのではなく、雨をつかさどる龍神様のお怒りだと考えていたようです。
確かについ先月彦根で起きた竜巻などの映像を見ると、龍神様の存在を想像するのも無理はないかと、思ったりもします。
まして自然科学の知識や情報が無い、陰陽道が社会の共通認識であった時代の事であればそんな風に思い描く事もまた、無理もなかっただろうと思っています。
そして同じことが実は祇園祭の御霊会や、祇園神社の神様「蘇民将来」の信仰にもつながってくるのです。
周囲を比叡山や北山等の山々に囲まれた山城(背)之國京都では、梅雨の時期には高瀬川や鴨川・桂川・木津川といった河川がたびたび氾濫し、市井の人々に大きな被害や犠牲をもたらせて来ました。
そして、その氾濫や水害に伴って感染症や伝染病といった疫病が広がり、そこから更なる二次被害や犠牲者が発生してきたのです。
それは現在でも医療関係者が、岡山や広島・香川の河川の氾濫地域で一生懸命感染症対策を講じていることから見ても、想像することが出来るます。
祇園祭はちょうどこの7月の中旬に 二度にわたって催されますが、それはこの時期の集中豪雨と深いつながりがあるようです。
集中豪雨による河川の氾濫が起こる事や疫病が発生する事を、祭りといった季節の行事とする事で注意を喚起する、という目的もあったのだろうと思われます。
祭りという行事を通じて、集中豪雨への意識付けや備えの予告といった効果を狙った事も、あったのではなかったかと思います。
そして同時に、河川の氾濫や感染症等の疫病によって亡くなられた方々の、鎮魂のための御霊会であります。
そしてスサノウノミコトや蘇民将来という、伝染病に打ち勝つ霊力を持った神様たちを主神として祀ることに成るわけです。
そのような事があったから安田義定公の領国である、遠州飯田の祇園神社を初め全国の水害に悩まされた地域では、八坂の祇園神社を招聘し地域の守り神とし又祇園祭を行って来たのでしょう。
今まさに行われている博多の祇園祭なども、そういった集中豪雨や疫病の発生を思い起こさせ、また退散させるための行事として執り行われているわけです。
その意味では祇園神社(八坂神社)が祀られ祇園祭の行われている地域というのは、かつて集中豪雨などによって河川の氾濫や、その後の疫病の被害に見舞われた地域であったという事を、知ることも出来るでしょう。
自分の居住地域に祇園神社や八坂神社が在り、祇園祭の風習が残っている地域の方々は先祖が残してくれた警告に思いを馳せ、自然災害がいつでも起こりうる地域である事を自覚して、災害から身を守るために常に備える事などが、有効だと思います。
日本全国に鎮座する「八百万(やおよろず)の神」というものはそう言った、先祖や先住者が残してきた知恵や警告の、記憶や記録の一つなのではないかと私は想っています。
因みに今年の八坂祇園祭は7月17日と24日だそうです。
W杯で日本代表に言及する時、時々目にするのはこの「日出づる国」という形容詞である。 とりわけイタリアやスペインなどの南欧においてその傾向がある様に思う。
あるいはこれは、マルコポーロ以来の「黄金の国ジパング」日本に対する形容なのかもしれない。
ともあれ日本には「日出づる国」という形容がヨーロッパにおいては、わりと付きまとうのである。
この言葉はかつて、聖徳太子が随の皇帝に対して親書を送った時に用いられた文言として日本でも知られている。
その言葉には大国随に対して、小国日本のプライドが窺えるのである。
その「日出づる国」の根拠は、いくつかある様である。
例えば、極東の中でも最東北に位置する国が日本である、という物理的な問題。世界で一番初めにその日の太陽が出るのが極東アジアの日本なのである。
近年はオセアニアの国が認められ、その物理的なポジションは微妙になりつつあるが・・。
しかしまぁ、歴史のあるヨーロッパにおいて日本はやはり、極東の国日出づる国なのである。
更にまた、「黄金の国JAPAN」なのである。
太陽のまぶしさはやはり黄金の輝きに通じるのであろう。
この言葉は、金の産出が由来しているように私は想っており、それは江戸時代初期にキリスト教の宣教師が、バチカンに送った蝦夷の国松前藩についての報告書が原因であったように私は思っている。(ご興味ある方は『蝦夷金山と甲州金山衆』を参照ください)
日本を象徴する国旗もまた太陽であり、日章旗である。
日の丸と君が代に関しては様々な思いや意見があるから、その点についてはここでは敢えて触れない。私自身は神道を尊重するが、民族主義者でないからである。
話は変わるがこの週末私は山梨県の甲州市を訪ねた。
いつものように安田義定公の痕跡というか、足跡を訪ねたのである。
そして今回は甲州市の市街地を遡り、大菩薩峠に至る途中の古刹「雲峰寺」を訪ねた。
寺の周囲は針葉樹に囲まれた山峡の山間地である。8世紀の中葉に行基が開山した歴史ある寺であるという。
私はその寺の創建から3百年近く後にこの地に領主として生きていた、義定公の痕跡が何か残っていないだろうかと、そう思って訪ねたのである。
その寺の宝物殿に件の「日章旗」が納められていたのである。
社伝によれば、武田勝頼が徳川・織田軍に追い詰められ自刃する際に当寺に、甲斐源氏伝来の御旗「日章旗=日の丸」を、奉納したという事である。
その日章旗は甲斐源氏の始祖である新羅三郎源頼光が、父親の頼義より受け継いだものらしい。と同時に甲斐源氏伝来の宝物「御旗、盾無し」の「御旗」という事に成るらしい。
かつて神功皇后が朝鮮新羅を征伐する際に、大分の宇佐八幡宮に奉納した御旗であると言い伝えられているモノらしいのだ。
その「御旗」はとても存在感があった。
御旗の一部しか残っていなかったが、それでも存在感があった。
多分絹織物によって製作されたのではなかったか、と思われたのだがとても存在感があり、その「御旗」に精神的な重さを私は感じたのである。
現在の国旗日の丸の軽さやチープさとは明らかに違う代物であった。
「神功皇后奉納」を模したモノとされる「御旗=日章旗」は将に、太陽の化身を感じさせたものであったのである。
その「御旗」に「日出づる国」の言の葉を感じ、その「言の葉」の化身を私は感じたのである。白と赤のチープな大量生産の日の丸に代わって、絹でできたハンドメイドの橙橙色の日章旗が、若し日本代表のW杯の応援席に棚引いていたら、と思わず私は想像してしまったのである。
きっとその「御旗」を見た人々は「日出づる国」を実感し体感するのではないかと、そんな風に妄想したのである。
いつの日かW杯の応援席に白と赤のチープな日の丸に代わって、この神功皇后の御旗を模した、存在感のある日章旗のレプリカが旗めいて欲しいものだと、そんなふうに「雲峰寺」の「御旗」を見て夢想したのであった。
そしてその御旗を体感した時、世界も「日出づる国」日本の名前の由来を感じることが出来るかもしれないと・・。
因みに「雲峰寺」には安田義定公に関係する遺物や史跡は無かったが、寺の境内でかつて埋蔵物として発見された「鎌倉時代の経典」があるらしいのだが、ひょっとしたらそれは義定公が奉納したものだったかもしれない、と根拠もなく夢想してはいる。
いつの日か機会があったら、その点を確認したいものだとそう思っている。
「御旗」:甲州市「雲峰寺ホームページ」より
先週末の30日早朝に、私の住んでる大樹町でロケットの打ち上げがあって、全国版のニュースでも取り上げられていた。
結果は残念なことに、今回も失敗に終わったようだ。
去年の今頃にも打ち上げが行われ、地上20kmぐらいの場所でコントロールできなくなって自爆した、かと思う。
宇宙ロケットMOMOは、名前の通り「百km」上空に到達することを目標としていたから、20%の達成率で終わってしまったようだ・・。
今年のGW期間中にもMOMO2号機が打ち上げられる予定だったが、設計上のミスが判明し中止・延期となり、それが6月30日に成ったという次第である。
直前に設計ミスが判明したことを聴き及び、再開には相当時間が掛かるかもと思ったものだが、2か月ぐらいで再開することを知り、大丈夫かと思ったものだ。
このロケットが大樹町で打ち上げられるのにはJAXAの存在が大きいようだ。
わが大樹町にはJAXAの実験用宇宙開発基地が在るからだ。
鹿児島の種子島に並ぶ基地ということに成るが、その存在はあまり知られていなかった。
JAXAの有するインフラに目を付けたのが、インターステラテクノロジーズ(以下ISTと称す)という宇宙ロケット開発のベンチャー企業である。
オーナーは、かのホリエモンである。
ホリエモンはベンチャー企業に対しては前向きだし、自らが起業家であった事からこのプロジェクトに積極的に関わって来たのだと思う。
もちろん彼自身が、宇宙ロケットに対するロマンを持ち合わせているのだろうし、アメリカ辺りで盛んなベンチャー起業家による、宇宙産業への参入といった動向からもインスピレーションを受け、更には少なからぬビジネスチャンスが在ることにも魅力を感じたのだろう、と思う。
また彼は自分の本気度や覚悟を示すために、住民票を大樹町に移している。
彼の壮大な事業計画によれば、ISTの宇宙ロケット開発事業が順調に行けば5,000人の雇用が大樹町に生まれる可能性がある、という事らしい。
現在人口が5,500人程度の大樹町の人口が、倍近くに膨れ上がることに成るのらしいのだ。町役場を始めとした関係者は、その夢に少なからぬ期待を示しているようだ。
放っておけば人口が、減少の一途を辿るだけの第一次産業中心の現在の大樹町である。
宇宙ロケットという最先端の科学技術産業の誕生や発展は、今後一体どのような将来像をこの町にもたらしてくれるのだろうか・・。
興味津々な想いで私は、傍観しているのである。
確実に言えることは、去年あたりから全国版のニュースでたびたび取り上げられていることから、大樹町の知名度Upに貢献していることは間違いないのだ。
そして地元にあるスーパーなどでは、これまであまり目にすることの少なかったオタク系の風貌をした、独身と思われる若者達が買い物している姿であり、千葉・神奈川・埼玉・茨城といったエリアの、ナンバープレートの自動車の姿である。
どうやら宇宙ロケットの影響が少しずつ、南十勝大樹町の生活の場面にも登場して来ているようだ。
これからの街の変化・変貌が楽しみではある。
W杯の日本代表の戦いは、今回のポーランド戦で一次リーグを終え、何とか突破することが出来て、ひと段落ついた。次の試合は7月3日のAM3時からのベルギー戦である。おかげで2日の夜は早い時間から、寝ることに成るであろう。たぶんアルコールの力を借りて・・。
さて水ダコ占いの話である。
今回のW杯日本戦の楽しみの番外編として「水ダコ占い」があった。
確かコロンビア戦の前日だったかと思うが、日本放送協会の北海道限定の夕方の情報番組で、この話題を取り上げていた。偶然そのニュースを私も目にした。
北海道北西部の小さな街小平町の漁港で、水ダコを捕獲・販売している漁師が遊び心で始めたイベントだ。
その日に獲れた水ダコの中で一番活きのよいタコを選んで、サッカー日本代表の1次リーグ全試合の勝敗を占わせたのである。
多分この漁師の頭には、4年前のブラジルW杯の時にドイツで行われた、タコ占いの記憶が残っていたのではなかったか、と思う。
確かパウル君(?)とか言ったと思うが、そのタコの勝敗予測が的中しドイツのマスコミも大きく取り上げていたのだ。
そしてその的中率の高さのゆえに世界中のサッカーファンの間で、一躍そのタコの存在は知られ彼はヒーローに成ったのであった。
⚽ ⚽ ⚽ ⚽ ⚽
おそらく世界中の多くのスポーツ系番組などで、彼の活躍は放送されたと思う。
地球の反対側の日本に居た我々でさえ知っているほどの、ニュースに成ったのであるから・・。
小平町の水ダコはその地名をもじって「ラビオ君」と名付けられていた。
で、そのオビラ君の的中率はどうだったかというと、100%だったのである。
「コロンビア戦には勝ち」
「セネガル戦には引き分け」
「ポーランド戦には負ける」と彼は占い、結果はその通りに成った。
この予測の件はその後ネットの世界では、相当拡まっていったようだ。
私は偶然その番組を見ていたから知っていたので、このHPの扉のコラムでも何回か書かせてもらっていた。
で、昨日の結果を見てその的中率が100%であることに改めてびっくりし、今度のベルギー戦でもぜひとも事前予測をしてほしいものだ、と思っていた。期待もしていた。
ところがどうやら、かの水ダコ「ラビオ君」はすでに出荷されてしまったらしい。
これから、という時にである。私はとても残念な想いがした。
その残念な想いの一つは、言うまでもなくW杯の番外編として無邪気に楽しむことが出来なくなった事に対して、である。そしてもう一つ残念に想ったのは、北海道の小さな街「小平町」にとって、その知名度を世界中に拡げるチャンスを無くしてしまった事について、である。
かの水ダコ「ラビオ君の勝敗占い」をイベントとして継続して行っていれば、その期間中マスコミは確実に話題とし、ニュースとして取材し・発信し続けたであろう。
その間「小平町」「小平の水ダコ」の名は日本中はもちろん、予測が的中している間は世界中のニュース番組やスポーツ番組などで、話題やニュースに取り上げられた可能性があったからだ。ちょうど4年前のドイツの「パウル君(?)」がそうであったように、だ。
これは見方を変えると、世界中に対して広告宣伝をしているのと同じで、将に「ブランディング化」をしているのと同じ行為なのである。
そういう意味では、「ラビオ君」を既に出荷してしまったという事は「小平町」や「小平の水ダコ」の知名度Up、ブランド化を放棄してしまったのに等しいのである。
北海道の片隅の小さな町は、「ラビオ君」を有効に活用する事を考えなかったがために、町の知名度Upやブランド化の手段を無くしてしまった、そのことが残念でならないのだ。マーケティングをやり損ねたのである。
今回のイベントはたぶん町役場の商工観光課や商工会から、TV局に入った情報なのだろうと思うが、彼らの頭の中にマーケティングの発想が無かったことは残念である。
同じ北海道に住んでいても道北日本海側の、その小さな町の名前を聞いたことも無かった私は、今回のイベントで小平町の存在そのものを知った。水ダコの産地であることも知ることとなった。
ブランディングやマーケティングとはそう言ったものなのだ。
今ではひょっとしたらスーパーや料理屋で、既に切り身に成ってしまっているかもしれない霊感豊かな水ダコの運命に、想いをいたしながら私は合掌しよう。
実はこの週末にお寿司を食べに行こうと思っているが、息子の家のある神奈川で北海道の水ダコを口にする機会があるかどうか判らないが、その時タコを食べるようだったら「ラビオ君」をしのんで、合掌してから食べようかと、そんなふうに思っている私である・・。
昨日の帯広駅前はお昼で、気温は13度であった。
そこから1,200kmほど飛行機で南下した羽田はPM4時頃で31・2度という事だった。
天気予報を見て今週は30度台が続く、という事で覚悟はしていたし半そでのシャツだったから、多少ムッとはしたがこんなもんか、といった感じだった。
問題は帯広の方で、この6月下旬でも時折13度なんてことがある。
街ゆく人の多くが長袖着であったが、彼らの方が環境に適応していることを示していた。
北海道がずっとこうかというと、決してそうではない。
この前の23・4日の週末は、25・6度で将に初夏の陽気だったのだ。
しかし油断していると、昨日の様な気温にもなるのだ。
やはり北海道の気候は、寒冷地適用なのだ。言うまでもないか・・。
帯広空港に向かう間、南十勝の大樹町からバスで帯広駅前に105分ほど移動した。距離的には7・80kmである。ちょっとした旅行である。
かつて国鉄の広尾線が開通していた頃は、1時間足らずで帯広にも行けたのであろうが、私が越してくるずっと前に廃線に成っていて、私は利用したことがない。
その105分程度の間私はバスの最後部座席で、過ぎ行く広大な十勝の畑や牧草地を眺めていた。
この季節だと「ジャガイモ」「デイトコーン(トウモロコシ)」「甜菜(グラニュー糖の原料)」「小麦」といった農作物が、緑の葉を大地の絨毯のようにして見渡す限り拡がっている。今年は天気も良く、適度に雨も降っていて十勝の農作物は順調に育っているようだ。
2・3年前みたいに夏場に台風が北海道に上陸することが少なければ、豊作に見舞われるであろう・・。
帯広近郊は「ジャガイモ」「甜菜」「小麦」「長芋」といった作物が主流であるが、わが大樹町は天候が安定しない土地柄であることから、上記作物ではなく酪農が主体である。
将に寒冷地で、痩せた土地と言われるエリアだから帯広辺りの農作物は育たない様だ。
その代わり牛や馬の畜産物の繁殖や育成には適しているようだ。
安田義定公の領地「乙女高原」「朝霧高原」「森町三倉」「笠原の牧」と似た自然環境なのである。
酪農の盛んな大樹町は5,500人程度の人間に比して、3万頭前後の牛が飼育されているという。ざっと6倍といったとこか・・。
今の大樹町では、横浜市よりも広い町域において盛んに牧草の刈り取りが行われている。
そしていたるところで、と言っても牧草地でだが「牧草ロール」が造られゴロゴロと転がっている。直径1.5mほどで400kg弱の牧草ロールは、半年ほど先にやってくる冬に備えた備蓄なのである。
因みに牧草ロール400kgは、牛1頭が一ヶ月に消費する量なのだそうだ。
北海道の農民たちはみなアリさんなのである。来たるべき寒い寒い冬を見越して初夏から晩秋にかけて、2度にわたって牧草ロールを造っている。私の様なキリギリスには到底真似ができない。
今日のように日が永い初夏は、早朝4時頃から日没7時過ぎまでの長時間を、アリさんのように働いている。
それを見るたびに十勝の農民たちは働き者だと、つくづく想いリスペクトしてやまない私である。
昨日の6月21日は夏至であった。
言うまでもなく一年で昼が一番長い日で、昨日を境に12月の冬至に向かってだんだん昼が短くなって行く。
因みに今年の冬至は、12月22日という事らしい。
北海道は首都圏と比べると時間がだいたい30分ほど早い。
九州は逆に30分ほど遅いのだから、北海道と九州とでは一時間ほどの時差があると思えばほぼ間違いない。ロシアやアメリカの国内の時差に比べたら短いものであるが、その時差が日本にもあるのだ。
時差があるという事はどういうことかというと、日の出や日没がそれぞれ早くなったり遅くなったりする、という事を意味する。
具体的な事を云うと、この時期私の住んでる南十勝だと午前4時頃にはすでに空が白み始め、照明がなくても屋外活動が可能になる。
これが首都圏だとたぶん4時半前後、九州だと5時前後にそういう状態になるのではないかと思う。で、日没はというとこちらでは19時前後に、そして首都圏と九州ではそれぞれ19時半、20時頃という事に成る。
私は仕事で宮崎県に行くことや親戚のある熊本に行く機会があるから痛感するのだが、九州の夏はホントに日が永いのだ。
九州の人々にとっては当たり前のことなのだろうが、関東や北海道から行くとその永さに驚かされる。日本も広いものだと、改めて思ったりするのだ。
そして北海道に住むように成ってから、私が感じ始めたものに「白夜」がある。
白夜というのは夜のない状態だと思えば良いのだが、北欧辺りでよく使われる言葉であり概念だと思うが、本州や九州辺りに暮らしていてもこの白夜の概念については、なかなか理解できないだろうと思う。かつて私自身がそうだったから・・。
しかし北海道は別なのだ、こちらに住んでいて今の夏至からお盆の頃までの5・60日間は白夜を感じることがある。
とりわけよく晴れる日にはそれを感じることが多い。
自然科学的には、緯度の高さがもたらす現象なのだろうが・・。
若いころにはやった歌に森繁久彌の「知床旅情」という歌がある。
この歌に「白夜」という言葉が登場するのだが、かの森繁久彌も映画のロケで知床半島に逗留した際に「白夜」を体験したのだと思う。
その時のある種の感動や驚きが、あの歌詞には込められているのではないかと、私は感じている。
知床はわが南十勝の大樹町より更に200㎞ほど北北東に位置し、緯度の高いエリアの街なのである。
夏至の翌日
牛歩
ほかならぬ昨日のW杯のコロンビア戦の事である。
昨日のコロンビア戦に際しては、コロンビアが圧倒的に優位であるとの下馬評が世界中にいきわたっていた。
私自身それに近い予測をしていた。
しかしパラグアイ戦の布陣と戦い方を見て、このDF構成ならひょっとしたら勝ち点1以上は期待できるのではないか、と思い始めたのは確かだ。
サッカーは攻撃陣に目が奪われがちであるが、実はDF陣の安定や充実がないと勝てないスポーツなのだ。他のスポーツも同じかもしれないが、ディフェンスすなわち敵の攻撃からゴールを守ることが安定してないと始まらないのだ。
野球で言えばバッテリーが安定してないと試合が締まらないのと同じだろう。今回の日本代表は、パラグアイ戦ではその安定感が見られた。
2点入れられたが、あの2本のシュートは防ぐのは相当厳しいといえるレベルの高いものだった。しかしあの2点でとどめたのが良かったのだ。
そしてDFが安定すると、それに連動するように攻撃も安定し、のびのびと展開出来るようになる。日本の攻撃陣は結構いい線行っているから、のびのびと展開できるように成れば結果にも期待が持てる。
パラグアイ戦では乾と香川の連携や、武藤との絡みも結構良かったし柴崎がアクセントをつけていたように思える。
昨日の試合のスターティングメンバーを見て、私は勝ち点1以上が期待できるのではないかと予測していた。
パラグアイ戦の布陣がベースに成っていたからだ。
懸念材料はGKの川島と、センターバックの吉田だった。案の定川島は避けることの可能な得点を許してしまった。ブラジル大会の時も同様のことがあったが、川島は到底一流のGKとは言えない。
東口か中村の方がよっぽどましだと思っている。
二人を比べた時、中村のあのギラギラした顔つきは期待しても良いのではないか、と思っている。年齢も22・3歳でこれからの成長が期待できる選手だ。
昨日のパフォーマンスを見て、西野監督が次のセネガル戦で誰をGKに選ぶのか注視したい。
その西野監督だが、彼の選手交代の采配はおおむね適切だと思う。香川や柴崎を先発させて、疲れの現れてきた後半の半ばぐらいから流れを変えるべく本田を投入したことや、2-1でリードしてから守備を安定させるために山口蛍を投入したのは、理にかなっていた。
それと彼はハーフタイムにロッカールームで選手に、後半何をすべきかを的確に指示している様に見れる。
パラグアイ戦でもそうだったが、昨日の試合でも前半の硬直していた状態をチェンジさせることが出来たのは、ハーフタイムにロッカールームで行われた修正の指示が、的確だったからだ、と推察できる。緊張している選手の心をほぐすユーモアも、西野監督にはあるようだ。パラグアイ戦の時の乾への対応がそれを示している。
いずれにせよ、ハリル前監督から西野監督へのチェンジは準備期間の少なさもあって心配していたが、どうやら成功だったといえそうである。
今の布陣やハーフタイムの対応などからは、彼の手腕をある程度安心して観ていられる。
あとはGKを換えれば更に安心できるのだが・・。
吉田の扱いは、時折みられるポカが心配だが、チェンジは難しいかもしれない。
チェンジするとしたら鹿島で昌子とペアを組む植田がよいと思っているのだが、監督の腹の内はどうだろうか・・。
いずれにしても、DFを安定させられればこのチームは結構いい線行けるように思う。Best8までは期待したい・・、と思っている。
25日のセネガル戦が待ち遠しい、今日この頃である。
牛歩
今朝の8時ころに大阪北部を中心に震度6弱の地震が発生したという。
3人ほどの方が倒れた塀などの犠牲に成って亡くなられたという事です。犠牲に成られた方にはお悔やみ申します。合掌
震度6弱の地震というと、私がこれまで生きてきた60数年の間に体験したことのない揺れである。
私の体験は東日本大震災の時の5弱と、2年ほど前の熊本地震のやはり5弱であった。
7年前の時は赤坂で会議をしている最中であった。
強く長い横揺れから、地震の規模が大きく震源地は相当離れているだろうと推察した。
会議室を出て向かった窓の外では、鹿島建設の本社社屋が工事中で、社屋に掛かっていた大型クレーンがユワーンユワーンと、大きく揺れていたのが目撃されよく落ちないものだ、落ちたらビルの周辺に大被害が起こるに違いない、と気を揉んだ記憶がある。
午後3時の14・5分前だと思うが、それからは公共交通機関が全てマヒしその夜は、会社の会議室で同僚と寝たことを覚えている。同僚のイビキのすごかったことも忘れられない。
翌朝早朝、何とかJR上野駅にたどり着いた私は、なかなか開通しない常磐線を4時間以上待ちながら、駅待合の大きなコンコースに映る大型TVの映像で、福島や宮城・岩手の津波のすさまじさを見た事を、今でもはっきりクッキリ映像とともに覚えている。
前の夜の気仙沼だかの港町が炎に包まれる映像もすごかったが、津波の恐ろしさを痛感した。
2年前の熊本地震の時は宮崎に出張していて、クライアントとの会食がそろそろ終わる、というタイミングでホテル8階のレストランで、体験した。
スマホの災害アラームが一斉に鳴り、東京から向かったメンバー達は東日本の体験があって一斉に反応したが、宮崎のクライアントは何が起きているのか判らなくって、戸惑っていたのが印象的であった。
日本という地震大国で生きていく以上、地震の災害や津波の事は常に頭の片隅に置いておかなくてはならないと自覚しているので、自分がパニックに陥ることはないものと思ってる。人間は自然の前では常に謙虚でなくてはならない。
そうしないと生きていけないからだ。
しかし、原発の災害などは事前に対応が可能だと思っている。
関西電力は日本海側の福井での原発経営に熱心だが、地震大国日本に原発は最大のリスクであるという事を忘れてはならない。
東日本大震災で学んだ教訓である。
目先の利益しか考えない企業経営者と、想像力が乏しく企業献金にしか関心のない愚かな政治家と、その政治家を選ぶ理性の足りない有権者達の犠牲には成りたくないものだ、と大阪の大地震の報を聞いて改めて、そう思う私である・・。
牛歩
アメリカの花札大統領と、ロケットマンが先日「世紀の会談」という触れ込みのイベントを行った。数か月前まで一触即発的な緊張感を漂わせていた両者であるが、平昌オリンピックや韓国の文大統領との南北首脳会談を経て、米朝首脳会談にこぎつけて上記の「世紀の会談」と相成ったわけである。
「核兵器の完全かつ不可逆的で、検証可能な放棄」「朝鮮戦争終結条約の締結」等々の華々しい前宣伝が盛んにおこなわれたが、蓋を開けてみれば
「決意表明」と「非具体的な計画表明」「ケータイ電話番号の交換」といった、ショボい内容だった。
花札大統領は盛んに「素晴らしい」「偉大な」「これまで誰も」とか言った形容詞・句を多用する人物である。ボキャブラリーが少なく、単純化された言葉を使う人間だ。
それは彼自身の問題でもあるが同時に、彼が常に意識している岩盤支持者と云われる人たちの問題でもある。
主としてアメリカ中南部の「錆びた鉄のベルト地帯」で生活している、高校卒のブルーワーカーで、かつては民主党の労働組合などを支持してきた人達でもある。
花札大統領が言っている様にこれまでアメリカ政治の主流からは「忘れられていた人々」で、グローバリズムのあおりを一番受けてきた層である。花札大統領の発言は常に彼らに対して発信されており、キーワードは「アメリカファースト」だ。
アメリカの経済学者が、花札大統領は政治をShow番組化していると看破していたが、全くその通りだと思う。
彼は長らくテレビのShow番組の司会をやっていたから、その勘所は心得ているのだろう。日本で言えば、みのもんたが総理大臣になるようなものか・・。
いずれにしても、Show化している大統領の言動であることを意識してからは、その発言にいちいち反応しなくなった。
言葉が軽く、その場しのぎな発言という点では、日本の政治家と同じだと認識している。政治家という職業にはそのような人間性が求められるかもしれない。
W杯に期待してよいのか・・。 2018.06.13 |
昨日の夜はスタメンの発表時点から、期待感はあった。
DF面での安定感が、予測できたからだ。
昨日までのDF陣には安定感は無かった。キーパーの川島を初め吉田も一試合の中で必ず1・2回はポカをやりそれが失点につながっているからだ。
槙野は前からの敵には対応できるが、横や後ろからの攻撃には不十分だ。
従ってこの三人が最後の防波堤だと安心して観ていられないのだ。
しかし昨日は鹿島のセンターバックがしっかりと固めていた。
GKは東口と中村だったので、彼らがどれだけ出来るのか見てやろう、という感じだった。
鹿島のDF陣には最後まであきらめない徹底的に守り切ろうとする、そういうスピリッツがある。これはDNAとして植えこまれており、鹿島の伝統的なチームポリシーに成ってる。
そしてこのDNAを植え付けたのはジーコである。Jリーグ創設期に鹿島を牽引し、鹿島のスピリッツは彼によって原型が作られてきたと、私は思っている。
サッカーはDFが安定しないと勝てないスポーツである。
どんなにFW陣が一流でも勝てないのだ。そのことはマラドーナが監督時のアルゼンチンを見ていればよくわかる。メッシやアグエロがいてもBest4には上がれないのだ。
それが日本代表がこれまでの親善試合でも勝てなかった要因だと思う。
8年前の南アフリカ大会でグループリーグを突破できたのもDFが安定していたからだ。中澤とトゥーリオがしっかり鍵をかけていたからなのである。
その守備陣の安定という基盤があって、前半外しまくっていた乾と香川がハーフタイムの西野監督のアドバイスによって修正して、結果を出すことが出来た。
二人のコンビはとても好く機能していたと思う。
それに柴崎も結構効いていた。流れや空気を換える役割を担っていたように思える。
相手DF陣は柴崎がボールを持つと緊張していたのが判った。予測できないプレーをするからだ。
岡崎も前線で結構よい働きをしていたと思う。レスターでいつもやっている様に相手の攻撃の芽を前線で摘み取っているのだ。
彼自身が得点することも大事だが、敵の攻撃を遅らせるというのもFWの大切な役割だ。
レスター同様スタメンで使って6・70分間経ったら、活きの良いスピードある選手に換えればよいのだ。
私は昨日のメンバーこそが今回の招集メンバー中ではAチームだと思う。
西野監督もどうやらそのように思っているようだ。試合後のインタビューから推測することができる。
このメンバー構成なら、一次リーグ突破に期待できるかもしれない、などと想った昨日の深夜であった。
昨日あたりから道東十勝には、氷雨が降っている。
氷雨という形容がふさわしい冷たい雨である。
昨日から最高気温は10度前後になっている。先週まで25・6度の日々が続き初夏を満喫していたから、身体もビックリしていることだろう。
昨日から暖房をつけ、厚手の服で身をまとっている。
やっぱり北海道なのだ。
オホーツク側は夏でも暖房を使うことがあるらしいから、さすがにそこまでには至らないが道東十勝でも、ママにこういうことはある。
この戻り寒気の原因は、先日来TVを賑わせている台風5号なのだろうと思われる。
今はもう熱帯低気圧に成って、仙台沖辺りに移ってしまっている元台風の低気圧のことだ。
日本列島の東南東にあるその低気圧に向かって、北北西のシベリア大陸にある冷気を含んだ高気圧から冷たい空気が、右下に移動してきているようだ。
首都圏辺りでは30度前後に成っているというから、北海道の10度前後の気候はちょっと信じられないであろう。
因みに今日あたりで一番過ごしやすいのは関西や中国・四国地方の西日本のようだ。最高気温が25度前後というから、快適だと思う。
この歳に成って私は、天気予報を必ずチェックするように成った。
若い時はあまり気にしていなかったが、やはり人類はと云うか生物は自然環境に左右される生き物だという事を痛感するようになってきている。
気圧の配置がどうなっているかとか、今週の予報はどうかとか、明日はどうか、3時間ごとの移り変わりはどうなるのかとか、そういった事がとても気に成っている。
これは私が北海道に住んでいるから、という事が原因ではないように思う。
夏の猛暑が続き台風の頻度が増えているとか、大雨にさらされているとか大雪が降るようになったとか云ったように、近年私たちを取り囲む自然環境の強弱がハッキリ、クッキリして来ていることに関係があるように思う。
地球温暖化といった地球環境の変化(悪化)への予防策として、自分自身で気象情報へのアンテナが、より強く張り巡らせるようになってきたのではないかと、思っているのである。
翻ってアメリカの花札大統領である。
アメリカ第一主義とかいう選挙目当ての看板を掲げ、地球環境を改善しようとするパリ協定から脱退してしまった。
目先の利益しか追求しようとしない男が、世界に最も影響力を発揮する国の指導者に成っている。そのことがもたらす結果に我々は好むと好まざるとに関わらず、振り回されることに成ってしまっている。不幸なことだ。
その花札大統領が今日これから北朝鮮のロケットマンと、歴史的会談をするという。
アメリカ第一主義や自身の指導力に影響を及ぼすこの秋の中間選挙に勝利するためという、近視眼的な利益追求に振り回されることがない様に、私は願って止まないのである。
南十勝の楼亭の周囲は数十本の樹々に囲まれている。といっても、三面だけであるが。
その樹々には少なからぬ鳥たちが食事に来たり、パートナーを探しに来ることがある。
たぶん、鳥には樹々や草花に参集する餌の虫が目当てであったり、そのために集まる雌鳥たちを相手に雄鳥たちがやって来るのであろう。
雄鳥は婚活のために、盛んに美声を発揮する。
自分がいかに上手に歌が唄える優秀で、美声の持ち主の鳥であるかを雌にアピールするために、であろう。
丹頂鶴が婚活に自らの羽を広げてアピールするのと同様だろう。
鳥たちの美しく立派な羽根も、美しい鳴声も雌鳥の関心を引くための行為であり、それによって自身のDNAを残すことができるのだ。
そしてその生物的な営みのおかげで、私は時に丹頂鶴を眼にすることが出来るのであり、鳴き声を聞くことが出来るのである。
GWの前後には丹頂鶴や白鳥が北帰行のための、必ずしも美しいとは言えない声(音)を頭上高くに聴くのであるが、その後は美しい小さな鳥たちの音色を聞くことが出来る。
先月は主として鶯の鳴声であったが、今月に入ってからは郭公の甲高い声がそれである。
その名前の通り”カッコー””カッコー”と彼らは連発するのであるが、その音色は透き通っていて爽やかである。
初夏の空気感にとてもマッチしている様に、感じている。
季節の鳥たちの音色を楽しめるこの季節私は、ここに居ることの幸せを感じるのである。
運が良ければ、アカゲラを見ることも可能だ・・。
どうやら関東以西は軒並み梅雨に入ったようだと、TVの気象情報は伝えている。
私は今週の火曜日から十勝に戻ってきているので、梅雨は知らない。
私が首都圏に居た10日ほどはまだ快晴で、最高気温30度前後の暑さ一歩手前の、比較的過ごしやすい気候であった。
そして北海道である。
ご存知のように北海道には梅雨がない。
学生時代京都に居た時、そのことを函館出身の友人に問うと、梅雨前線が北海道までは上がらないから梅雨が無いのだと、教えてもらった。
因みに梅雨をもたらすこの季節の水蒸気の塊は、遠く離れたインド洋沖に発生するのだという。それがヒマラヤ山脈を次々と越えて中国、朝鮮半島を経由して遥か日本までやって来るらしい。
そのヒマラヤ山脈を越えるとかいう梅雨前線も、どういうわけか津軽海峡は越えないのだという。津軽海峡恐るべし、なのであろうか・・。
北海道に移って10年近くになるが、家人は当初北海道に梅雨は無いけども、この時期雨が降ることに驚いていた。その事に若干の不満もあるようだった。
しかし私にしてみれば、6月下旬ころから始まるあの蒸し暑い梅雨がないのだから、天国である。
私にとって、6月下旬から9月中旬まで続く「蒸し暑さ」と「灼熱の真夏日」「熱帯夜」が無いだけでも北海道に来た価値があるのだ。
たとえ11月下旬から4月上旬の半年間に、マイナス20~30度の日々が続いたとしても・・。
昨日10日ぶりに十勝に帰ってきた。
その十勝帯広空港の到着ロビーには、実寸大のばん馬像が在る。
この像は報道ステーションの特集で制作した実寸大の「ばん馬」だという。
高さ2m以上あるこの像は、「帯広ばんえい競馬」において現在も活躍している、北海道の農耕馬「ばん馬」の像である。
明治以来の北海道の開拓農民の貴重な労働力であった「ばん馬」も今では、一部の好事家を除いては機械に取って代わられている。
この空港の「ばん馬像」は、ほぼ実寸大だという。
とても大きく、筋骨隆々としているが、その眼は優しい。
太古以来人間の手がほとんど入らなかったかつての蝦夷地北海道で、開拓者が原生林を伐採したり耕作地化をする際に、この「ばん馬」はたいそう役に立ったものだと開拓者の子孫たちが云う。
帯広空港近くにこの「ばん馬」専用と思われる牧場が在る。
その「ばん馬牧場」が、年々規模を広げ飼育する馬の数も増やしてきている。
空港への送迎に来るたびに、私たちはその大規模化に遭遇している。
聞くところによると帯広のばんえい競馬も民営化を果たし、経営は安定して来ているという。喜ばしいことである。
かつて北海道の入植者にとって貴重な労働力であり、家族の一員でもあったに違いない大切な「ばん馬」がその役割を変えて、生き残っていることを嬉しく思う。
馬という動物はとても賢く、飼い主にもなつくという。
そのばん馬牧場に、最近観光客向けと思われる商業施設が新たに加わっている。
どうやら飲食施設があるようだ。
近いうちに訪れたいものだと、迎えに来てくれた家人とそう話し合った初夏の十勝である。
最近日本の官僚の質が低下しているとよく言われている。
確かに一連の不祥事や行動を観ていると、人間としてのクオリティに疑いを抱くような人間が多いようだ。
それも所謂トップクラスの官僚ほどそのように思う。
国家公務員の上層部の人達は20代の前半に公務員の上級試験を通った人達であるから、記憶力がそれなりに良く「優秀」な人達なのだとは思う。
その記憶力が売り物の優秀なはずの人達が平気で、国会即ち国民に対して嘘をつき記憶を失い、厚かましさを露呈している。
私は長い間公務員と言うのは、国民や市民・町村民のために働く職種だと思っていたが、どうやらそうでは無いことに気付き始めた。
もちろん中には、まじめで有能な公務員も少なからずいるものと思われる。
しかしそういう公務員は官僚機構のハイラルキーの中では、あまり高い地位には到達しないことが多いようだ。
そしてどういう人種がハイラルキーの高い地位に就くことが出来るのかと言うと、冒頭の様な「平気で嘘をつき」「公の場でのみ記憶力を失い」「厚かましく成れる」人種ではないか、と思いが至った。
私は昔から公務員をあまり評価して無かったが、最近は上層部の人間に対しては卑下するように成って来ている。困ったものだ・・。
もちろん中には「Im Not Abe」と言ってはばからない元上級公務員や元事務次官もいるが、彼らはまだまだ少数だ。
多分そういう骨のある上級官僚が増えたら、私の彼らに対する認識も変わるかもしれない。
政治家と言う官僚以上に厚顔無恥で、記憶力が低く、嘘をつく能力の高い、時には人間性すら失っている人種に使われ、人事権(昇進権)を握られている彼らに多くを期待するのは難しい事かもしれない。これはきっと構造的な問題なのだろう。
そう言えば最近の政治家は二世議員やら祖父を尊敬してやまない世襲議員ばかりで、有能な官僚上がりの政治家少なく成ってるように思えるが、私の記憶違いだろうか・・。
そしてこれからの時代「記憶力の良い」「優秀な」人種は、早晩AI(人工知能)に取って代わられる事になるだろうから、だんだん「記憶力」や「優秀さ」がウリの人種は、自分の居場所が無くなって来るに違いない。
私の懸念は時代と共に無くなるかもしれないな・・。などと思う今日この頃である。
先日茅ケ崎で、90歳の女性が横断歩道で4人の人をはねて、死傷させたという。
そのニュースを聞いて、私がまず驚いたのは運転手の年齢である。
90歳でなお、車を運転するという。
それは感心するというより、あきれた驚きであった。90歳の老女が事故を起こした事には驚かなかった。それは大いにあり得ることだからである。
そして思ったのは家族は一体何をしていたんだろうという事と、この三月に免許を更新したばかりという事である。
本人の意思がどうであるかは関係なく、家族も警察もこの高齢者に車を運転させた事に、驚きと憤りとを感じた。
確かに現在の法律では年齢制限は無いようだが、だからと言って野放しで良いのだろうか・・。
家族も勧告はしていたらしいが、強く禁止はしなかったようだ。
家庭内の力関係があるのかもしれないが、今回の事故の犠牲者はその老女の家族や年齢制限を設けない法律に、被害をもたらされた様なもんだと、私は思う。
個人の自由意志を尊重するというと聞こえは良いが、社会のルールとして規制すべきだと私は思う。歳を経れば判断力が衰えたり、とっさの対応が出来なくなるのは自然の摂理だからだ。
私自身は75歳くらいに免許の返上を考えてはいるが、80歳ぐらいが限界ではないかと想っている。高齢者の運転は決して褒められるべきものではないと、私は思っている。
その事を自慢げに言う人には、私自身は厳しい言葉を掛けている。
家族は鍵を取り上げるなり車を処分するなどして、厳しく当たるべきだと思う。
そして政治家や行政は、法改正を早急にすべきであると思う。
これ以上高齢者運転の犠牲者を出さないためにも・・。
私は強く、そう思っているのだ。
大相撲の夏場所が終わった。
優勝したのは鶴竜で、栃ノ心が場所を沸かせてくれた。
相撲という格闘技は、とてもシンプルで勝ち敗けがハッキリしている個人スポーツだ。
世界中にファンが少なからずいるのは、そのシンプルさに依っているのではないかと思う。
アメリカあたりではただのデブが裸でマワシを付けてやるスポーツだと、誤解している向きもあるようだが、実際の相撲を目の当たりにすると、認識を改めるという。
このスポーツを千年以上昔から愛し、継承し育てて来た日本人にはある種の共通認識があると思う。
それは勝つことに拘り過ぎて、品格と言うか品位を疎かにしてしまう取り口を是としない・評価しない、という事である。
勝つためには何をやっても構わない、手段を択ばない戦い方を良しとしない、という事だ。
今回優勝した鶴竜も時々体をかわしたり、張り手を連発することがあるが白鵬ほどではない。
白鵬の人気がその戦績ほど高くないのも、この事に依っていると、私は想っている。
翻って、日大のアメフト部の事件である。
勝つためには手段を択ばなかった、学校法人の常務理事でありアメフト部の監督の事である。
この問題が一月近く尾を引いているのは、もちろん彼自身や日大経営陣の対応の拙さにもよるのである。
しかしそれに加えて、勝つために手段を択ばないというその基本的な考え方に、日本人のメンタリティーが強く反発しているからではないかと、私にはそんな風に思えるのである。
それに油を注いでいるのは、自身の保身のために過ちをなかなか認めようとしない、潔さが欠落している点であろう。
監督やコーチの指示により追い込まれ反則を犯さざるを得なかった、二十歳の選手の潔さと対極にある対応である。
スポーツにおける品位はこう言った点にある様に私には思えるのだ。
さて栃ノ心はどうか。
かつての彼は、腕力や筋力で相撲を取っているように思えていたが、最近はがっぷり四つに組んでからの相撲に、替わってきているような気がする。
相手をしっかり受け止めてから、自分の技と力と経験で勝負する様に、替わってきているように思われるのだ。
ここ数場所の戦績は彼の取り口の変化、質的な変化と言っても良いように思うのだが、その結果がもたらしているのではないかと思う。
彼はまだ成長の過程にあると、私には思える。
彼が自分自身と闘いながら、もう一皮剝けてくれることを期待する私である。
昨日一月ぶりに首都圏に戻った。
バスで大樹町から帯広空港に向かう途中、旧国鉄広尾線「幸福駅跡」を通った。
とかち帯広空港までは、車で10分もしない田園地帯にその駅跡は在る。
駐車場には十数台の自動車が停まっていた。平日の昼過ぎだというのに訪問者は多いようだ。
この観光スポットには年間10万人近くが訪れる、という。一日当たり270人強だ。
殆ど交通手段が無い、といっても良い不便な立地からすると、驚くべき吸引力だ。
駅名が持つ吸引力、という事か・・。ネーミングの勝利か。
やはりこの駅跡には、神社か祠(ほこら)を立てるべきだと思う私である。
縁結びの神を祭神にしたら好かろう。
日本人の八百万(やおよろず)の神信仰の土壌にあっては、この様な観光客と言う名の参拝者の存在は、新しい神社の創設を暗に促しているものと思われるからである・・。
日本人は多神教であり、いろんな対象物に神と言う名の信仰対象を見出す。
日本人にとって神と言うのは、信仰者の想いが向かう対象物であるからだ。
年間10万人近くが集うこの「幸福駅跡」は、それだけの想いが在るのだから、日本人の所謂(いわゆ)る宗教観から言えば、充分神に成り得ると思う。
廃線に成って40年近くは経つと思う今日もなお、これだけの来場者が居るのだからその参拝者たちの想いに応えるべきではないか、などと想いながら空港のレストランで生ビールを呑んでいた初夏の一日である。
オレンジ色の車両が緑の牧草地に映える「幸福駅」跡地
このGWの終わりごろから盛んにメディアを賑わせていた、アメフトの日大DF選手の関西学院QBへの悪質タックル問題の真相が、昨日の当該選手の会見でやっと見えてきた。
あの試合のアフタータックルの異常さは、到底看過できるものではなかった。
サッカーの試合で言えば一発レッドの代物である。
私はあのプレーの後も当該選手が引き続きプレーをできた点にアメフトという競技の緩さといったものを感じた。
当該選手はあの後も複数回ラフプレーを行い、やっと退場になったがそれまでプレーを続行させたあの試合の審判にも不信を抱いた。
日本のアメフト界のレベルというのはこの程度かと、そんな風にさえ感じたのであった。
と同時に思ったのは、当該選手の選手生命はもう終わりだろうな、ということだった。
試合の後の日大の監督のコメントが、「厳しい試合」だとか「誇りに思う」という会見内容を知り、早晩監督やコーチもこの世界では生きていけないだろうと、思った。
その後関西学院大に、日大の副学長や当該監督が陳謝に行った際のコメントや対応も報じられたが、それらにも誠実さを感じなかった。
陳謝に出向き、辞職すればそれでいいだろう感が、漂っていた。
そして昨日の選手の会見である。
当該選手の会見を聞き、今回の彼のプレーがなぜあのような異常なものであり、試合後の監督のあのような会見内容だったのか、また関西学院行きの不誠実な対応だったのかに、すんなり納得がいった。
かの選手は追い詰められていたのである。監督とその配下のコーチによって。
20歳の若い人間にとって、今回の件はこれまで経験したことのない苦悩の日々であり試練であっただろう、と思う。
彼は10何年か続けてきた大好きな(たぶん)アメフトに別れを告げ、大人社会の理不尽さを身に染みて経験したであろうと思う。
会見を終えた彼が、なんとなくすっきりした印象を受けたのは、彼自身が人間的な成長を遂げた証であろうか・・。
そういう意味では、昨日の記者会見は彼自身にとっても良かったと思う。
彼のラフプレーの背景への理解が進み、不要な誤解は起こらないだろうと思われる。
そしてこれから苦悩と試練の日々を迎えるのは、日大アメフト部のコーチであり監督であろう。更に大学が不透明で釈然としない対応をするならば、日大自体が大きなしっぺ返しを受けるであろう。
アメフト部の存続はもちろん、大学の社会的評価は失墜し大学への入学希望者にもその影響は現れるだろう。少子化社会という現実がそれを加速させるのではないか、と思う。
今回の事件は刑事事件として処理され、法廷の場に上がる見通しだという。司法の場でも厳しく裁断されると思う。
そして当事者の誠実な記者会見という行為の持つ、影響力についても考えさせられた。
さて、我が国の国会では相変わらず官僚や大臣・首相たちが不誠実で、その場逃れの対応を続けている。
狸おやじたちは、今回のアメフト問題の一連の騒動から、何かを学ぶことがあったのであろうか。
まぁ、それは無いか・・。
政治家という人種や職業は、その手の種類の人間達の集合体であるから、今もなお政治家であり続けることができるのだろうな、などと思ったりもする。
とりわけ権力を握っている人種は、自ら変革する努力よりも権力闘争の方を好む人種だから、である。
しかし、狛江市の市長の例もある。これからの世論次第という事か・・。
昨日の夕方、6時を過ぎたころの事である。
我が聴囀楼の南に広がる牧草地を、周りに注意を払いながら歩む四頭のエゾシカが現れた。
紋別川という、日高山脈に源を発する川の土手沿いを歩いてきたようだ。
彼らの夕食時なのかもしれない。
近年北海道各地では、エゾシカの獣害が頻発しており農家が丹精込めて作った作物などが、少なからぬ被害を被っている。
本州辺りでは猿やイノシシが原因のようだが、北海道の主役はもっぱらエゾシカである。
この前もニュースでそのエゾシカを駆除する手法として、ナント吹き矢を活用する業者の事が報道されていた。ずいぶんとのどかな駆除方法だなと思ったものだ。
市街地近くの農場という事もあって、猟銃を使った駆除はできないという事らしい。
その吹き矢には麻酔機能があったという事だが、風向きの影響もあって吹き矢による駆除は成功しなかった、という。
安田義定公の逸話に、遠州の彼の領地でシカを7・8頭仕留めその鹿皮を将軍頼朝と頼家に献上した、といった事が『吾妻鏡』に記載されいたのを私は思い出した。
当時はもちろん、弓矢による狩猟である。
騎馬に乗って、動く鹿の群れを追いかけ射抜いた、という事であろう。
甲斐の騎馬武者の本領発揮、という事か・・。
かつて私はシカ肉を食べたとこがある、日光の鬼怒川温泉の奥の方であったが、その時のシカ肉の味は柔らかく鶏肉に似た味であったと記憶している。食べやすい味である。
今北海道の各地ではシカ肉を使ったジビエ料理などが、料理人たちによってメニューに載るようになっているらしい。
鎌倉時代の武将たちは、当時はどのようにして狩り取ったシカの肉を食したのであろうか・・。などと妄想しているうちに、四頭の家族の鹿たちは前足と後ろ足を揃えてピョンピョン跳ねて、逃げて行った。カンガルーが跳ねるような格好で。
私の食欲を察知して、かのシカの家族は逃げて行ったのであろうか、等と思ったりもしたのである。
今日、来月行われるサッカーW杯ロシア大会の日本代表の、一次選考の発表が行われた。
注目の本田・岡崎・香川のベテランたちが選考されていた。
今海外でも評価の高いポルトガルリーグの中島が外れたのは残念だったが、おおむね順当といった感じだった。
今回の選手選考の前に、ハリル監督の解任が先月にあり一騒動があった。
私はハリル監督のように、直前まで調子の良い選手を選ぶ余地を持っている選考方式は、悪くないと思ってはいたが、ハリルの場合はその調合(バランス)に問題があった、と思っている。
具体的には、去年の11月や12月ごろまではメンバーの半分くらいを固定せず調子のよい選手を試すのも悪くはないと思っていた。半年前だからである。
しかし今年の3月の時点でも5・60%の新メンバーを試すやり方には、どうかと思っていた。
残りの3か月になってもまだ中心メンバーが固まっていないことに?があったのだ。
3か月前なら7・80%は固めていないとまずいだろう、と思っていたからである。チャレンジするのは2・30%程度にとどめておくべきだったと、思っていた。
ハリル監督はこれまで2・3年間は日本代表の選手たちを見てきていたのだから、さすがに半年くらい前から中核メンバーは固めるべきだ、と思っていたのだ。
実際、この3月のヨーロッパ遠征での親善試合の戦い方を見ていて、個人プレーが目立ち組織としての連携や決まり事といったものが、ほとんど感じられずストレスのたまる試合内容だった。
試合後にキャプテンの長谷部の言っていた「チームとしての継続性や積み重ねが見られず、不安だ・・」といったコメントの通りだったのである。
長谷部の思いは見ている私たちも感じていたし、日本サッカー協会の首脳陣も同じように感じていたのかもしれない。
そういったことがあっての電撃解任劇だったのだろう。
しかしこの決断をした田嶋会長は、この判断については、責任を負うことに成るだろう。
意思決定者というものは、自分の下した結果には責任を負わなくてはならないのだ。それは権力を握るものの宿命なのだ。
脇とよさんの『砂金掘り物語』 2018.05.16 |
かねてより関心のあった『砂金掘り物語』を先日帯広図書館から借りてきた。
この本は、私の『蝦夷金山と甲州金山(かなやま)衆』の中でも触れているように、北海道の砂金や金山に何らかの形で携わる人々にとって、著名な著書である。
昭和31年に刊行されたこの本は、明治20年代に雨宮砂金採集団に参加した砂金掘り師「渡辺良作」が語る昔話を、甥の脇清吉氏がメモ取りしそれを基に妻の脇とよさんが、後日書物に取りまとめたものである。
この書物を読んでいると、明治中頃の北海道における砂金掘りの実態が実によく判る。
山形の小作生活から抜け出す野心を持っていた、良作とその父親達が北海道の砂金取りに人生の活路を見出していく実録の物語である。
当時の小作の置かれている環境やそこから這い出そうとしている人達にとって、常雇いの砂金掘りはアメリカンドリームを夢見て、ニューフロンティアを目指した欧州の移民達や、北海道に屯田兵等として入部した本州の開拓者に重なるものがある、と思って読むことができる。
もちろん、当時の北海道がいかに砂金や金山の天然資源豊かな未開拓の地であったかも、如実に知ることができる。
太古以来ほとんど手つかずの状況だったから、さもありなんなのだ。
そしてこの著書を通して、かつて鎌倉時代に蝦夷地を目指した甲州金山衆が、北海道南端の渡島知内界隈で遭遇した体験を重ね合わせて、想像することができるのである。
もちろん、その間7百年近くのタイムラグはあるのだが、雨宮砂金団の採金方法は原初的な手法で人海戦術であるために、かえって荒木大学たちの採金手法より拙いものだと思われるのである。
甲州金山衆の場合は、金鉱石等の精錬や冶金の技術を有する鍛冶屋集団(その数3百軒といわれている)などを伴っているから、より本格的で組織的なのである。
自然採集の砂金取り達より、はるかに高度な技術やノウハウを有して砂金取りや金山開発をしているからである。
しかしながら、彼らが初めて知内に上陸し手つかずの黄金郷を目にした時の驚きや感動は、渡辺良作たちが体験したものと同じだったのではないか、と想像できるのだ。
そんな風に想いながら、私はこの本をワクワクしつつ読ませていただいた。
いつの日か、砂金掘り師たちが登場する物語を描く機会があれば、この書の持つリアリティをぜひとも参考にさせていただきたいものだと、想っているのである。
十勝の長い冬が終わり春が訪れると、我が家の草むらの一画に行者ニンニクが生えてくる。
前住者の方が育てた野草である。
北海道では野山に行くと、運が良ければ遭遇すると思われるが、本州でも標高の高いエリアではみられるのではないか。ただ希少価値の食物らしく春先になると求める方が少なからずいるらしい。
注意を要するのは、行者ニンニクに似た野草で蘭科の植物を間違え採取して、食中毒になる方が毎年現れる。毎年ニュースで報道される。今年も亡くなった方が現れたようだ。
さて、この行者ニンニクはその名の通り修験者などが体力回復のために好んで食べたという。
近隣の方々もその効果を期待して、この時期求めるのであろうか・・。
私などは苦労せずに手に入るものだから、有難みがさほど沸かないが、ニラの一種だと思って採ってきて、調理に使っている。
採りたての行者ニンニクは、その名の通りニンニク臭さがするのであるが、体力回復のほどは殆ど判らない。しかし春先に生える野草だから、長い冬に蓄積された大地のミネラルをはじめとした栄養を、たっぷり含んでいるものと思われ、私の健康維持にも少なからぬ寄与をしているのかもしれない。
行者ニンニクを食べる度に私は、鎌倉時代初期に蝦夷地に渡った甲州金山(かなやま)衆も、春先には渡島(おしま)知内で食べたのだろうかと、思ったりもするのである。
牛歩
十勝にも本格的な春が来たか・・。 2018.05.12 |
昨日あたりから、私の住む南十勝辺りの気温も安定してきたようだ。
一昨日までは、温かい日と寒い日が行き来する「三寒四温状態」が続いていた。
しかしどうやら、それも昨日あたりで終わったようだ。今後は最高気温20度前後が続くと週間予報などで、予測している。
十勝は北海道でも道東といわれるエリアに区分される。
北海道は日高山脈で東西に線引きがなされ、大雪山系で南北が分かれる。そしてわが十勝はこの区分によると、右下の1/4に在るのであり東南地区ということになる。
北海道の中でも比較的暖かい方に属する。もちろん本州からすれば寒いのであるが・・。
現在の地に来て10年近くなるが、GWが終わるまで積雪につながるレベルの、雪が降ることを数回経験している。
その南十勝にもやっと本格的な春が来たのである。
周辺のエゾヤマザクラが開花して10日近く経つが、やっと満開になってきている。
これからは、春と初夏とを行ったり来たりの日々が続くのである。
「三暖四温」とでもいう日が、これから始まるのであろう・・。
牛歩
この時季、家の近くでは丹頂鶴が数羽から数十羽見ることが出来る。
どうやら彼らや彼女らは、エサを探しつつパートナーを探しているらしい。
オスとみられる鶴がしきりにメスと思われる鶴の前で、羽を大きく羽ばたかせている。
その行為は自分の持つ羽の大きさやすばらしさを、メスに見せつけているようであり
自分をアピールしている様に思える。要するに婚活をしているのだろう。
彼らはカップリングを終えると、たぶんこれからそう遠くない時期に、シベリア辺り
に向かうのではないかと、想われる。
2・3週間前に白鳥たちの群れが数百から千羽単位で群集し、飛行訓練を重ねたうえで
北へと向かったのと同じような事が起きると思われるからだ・・。
尤も、そのうちの何羽かは北帰行せず、つがいでこの大樹に残ることに成るのではな
いか。
私の住んでる大樹には夏でも何組かのカップルが残り、新たに誕生した家族を迎えて、
子育てしている姿を時折見かけるからである。
人口減が進むこの町では、夏もこの町に残る丹頂鶴のファミリーに住民票を与えたら
どうだろう、と思ったりもする春の一日である。