|
2018/5/16
|
|
脇とよさんの『砂金掘り物語』 |
|
|
かねてより関心のあった『砂金掘り物語』を先日帯広図書館から借りてきた。 この本は、私の『蝦夷金山と甲州金山(かなやま)衆』の中でも触れているように、北海道の砂金や金山に何らかの形で携わる人々にとって、著名な著書である。 昭和31年に刊行されたこの本は、明治20年代に雨宮砂金採集団に参加した砂金掘り師「渡辺良作」が語る昔話を、甥の脇清吉氏がメモ取りしそれを基に妻の脇とよさんが、後日書物に取りまとめたものである。 この書物を読んでいると、明治中頃の北海道における砂金掘りの実態が実によく判る。 山形の小作生活から抜け出す野心を持っていた、良作とその父親達が北海道の砂金取りに人生の活路を見出していく実録の物語である。 当時の小作の置かれている環境やそこから這い出そうとしている人達にとって、常雇いの砂金掘りはアメリカンドリームを夢見て、ニューフロンティアを目指した欧州の移民達や、北海道に屯田兵等として入部した本州の開拓者に重なるものがある、と思って読むことができる。 もちろん、当時の北海道がいかに砂金や金山の天然資源豊かな未開拓の地であったかも、如実に知ることができる。 太古以来ほとんど手つかずの状況だったから、さもありなんなのだ。 そしてこの著書を通して、かつて鎌倉時代に蝦夷地を目指した甲州金山衆が、北海道南端の渡島知内界隈で遭遇した体験を重ね合わせて、想像することができるのである。 もちろん、その間7百年近くのタイムラグはあるのだが、雨宮砂金団の採金方法は原初的な手法で人海戦術であるために、かえって荒木大学たちの採金手法より拙いものだと思われるのである。 甲州金山衆の場合は、金鉱石等の精錬や冶金の技術を有する鍛冶屋集団(その数3百軒といわれている)などを伴っているから、より本格的で組織的なのである。 自然採集の砂金取り達より、はるかに高度な技術やノウハウを有して砂金取りや金山開発をしているからである。 しかしながら、彼らが初めて知内に上陸し手つかずの黄金郷を目にした時の驚きや感動は、渡辺良作たちが体験したものと同じだったのではないか、と想像できるのだ。 そんな風に想いながら、私はこの本をワクワクしつつ読ませていただいた。 いつの日か、砂金掘り師たちが登場する物語を描く機会があれば、この書の持つリアリティをぜひとも参考にさせていただきたいものだと、想っているのである。 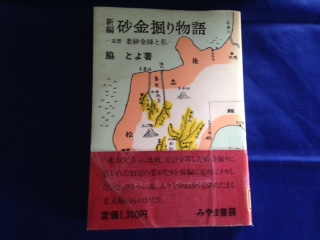 |
|
| |

























